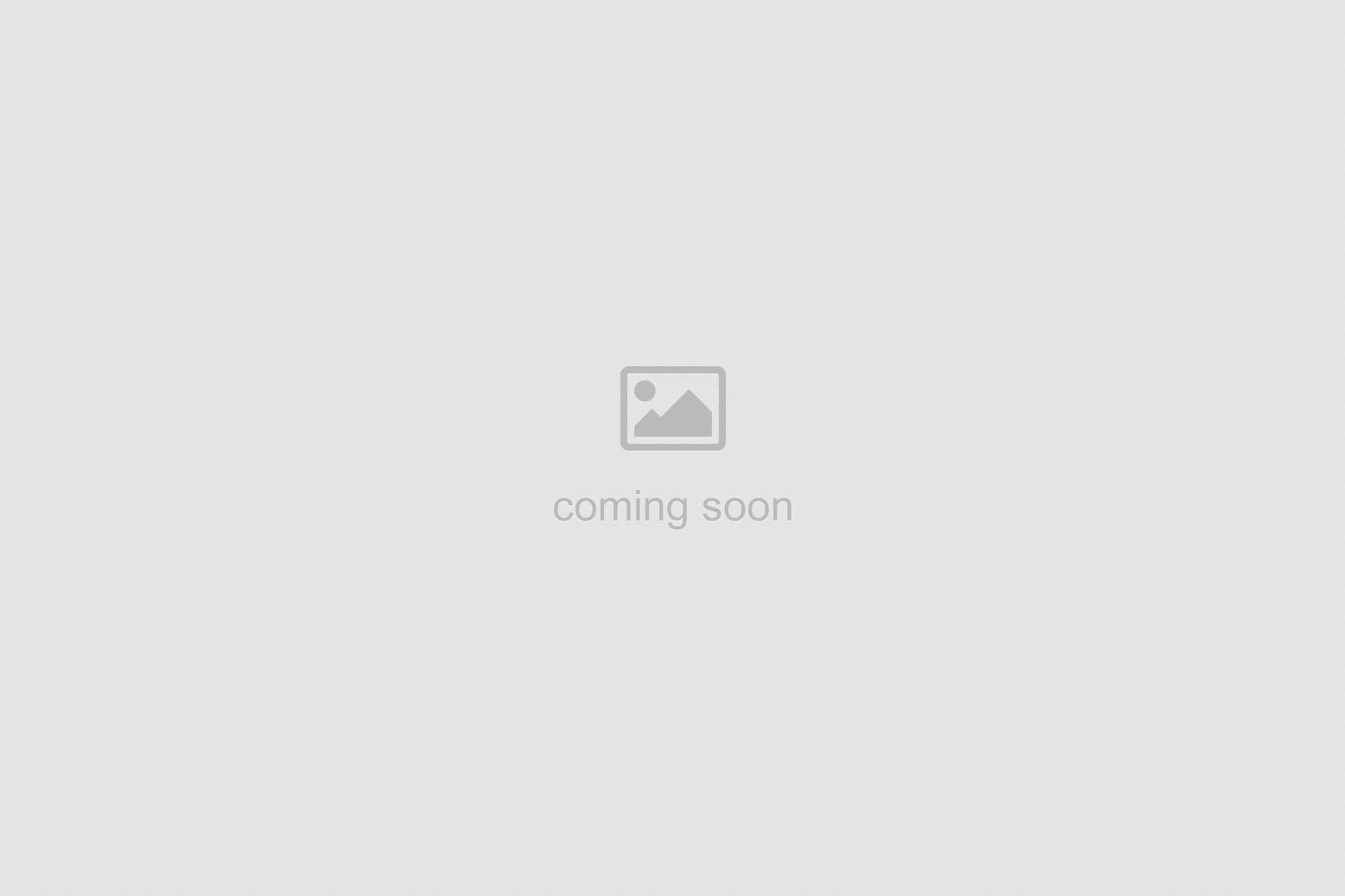行為無価値と結果無価値
行為無価値論と結果無価値論
刑法総論を勉強する際には、大体は学者の執筆した基本書を読むことになります。
基本書を読む際に、受験生が突き当たる問題が「行為無価値論の本を読むか、結果無価値論の本を読むか」ということです。
刑法学者によって、行為無価値論をとる人もいますし、結果無価値論をとる人もいます。
勿論、学説の相違自体は他のどんな科目にもあることであり、それぞれの学説の論拠を調べてどの学説が最も相応しいと思われるかということを考えるのが法律学習の重要な部分なのですが、刑法総論の行為無価値論と結果無価値論の違いは、一つの論点に留まらず刑法総論全体の理解の違いに結びついてきますので、受験生を悩ませることになります。
行為無価値論は、違法性の本質を、犯罪の行為に重点を置いて解釈する考え方です。
殺人罪であれば、人を殺害するという行為が違法の本質ということになります。
結果無価値論は、違法性の本質を、犯罪の結果に重点を置いて解釈する考え方です。
殺人罪であれば、人を死亡させたという結果が違法の本質ということになります。
両説の最大の違いは、故意・過失の検討をどの段階で行うかということに繋がります。
刑法総論においては「1.構成要件 2.違法 3.責任」の順で犯罪成立の有無を検討することになりますが、故意・過失をどの段階で検討するかの位置づけが各説によって異なります。
行為無価値論であれば、1番目の構成要件の段階で故意・過失を検討します。
結果無価値論であれば、3番目の責任の段階で故意・過失を検討します。結果無価値論は、構成要件や違法性をなるべく客観的に(つまり、人の心情であるとか主観的なことを介入させずに)理解しようとするので、3番目の責任の段階にて故意・過失を検討することになります。
ただ、司法試験等の受験を意識するのであれば行為無価値論のほうが良いと思います。
結果無価値論のデメリットの一つは、刑法総論以外の科目との整合性の問題です。
結果無価値論は、構成要件と違法の段階では主観的な要素(つまり人間の心情のような要素)を排除しようとするところが特徴ですが、刑法各論においては、例えば財産犯の検討において「不法領得の意思」という主観的要素を検討します。最初から構成要件の検討において主観的な要素が入り込むことを否定しない行為無価値論においては故意に追加して「不法領得の意思」を検討することについて違和感はないですが、構成要件と違法性において主観的な要素が入り込むことを否定しようとする結果無価値論において「不法領得の意思」を検討することについては強い違和感があります。
この点、例えば結果無価値論である林幹人教授は『刑法各論』(第2版)において「実質的に重大な法益侵害に向けられた意思を犯罪成立要件と解するほかないであろう」(193頁)と記述しておられますが、その「犯罪成立要件」が刑法総論においてどのような位置づけになってくるのか不明確であるという印象を受けます。
同じく結果無価値論の曽根威彦教授は『刑法各論』(第4版)で不法領得の意思を不要としており、理論的には一貫していますが、最高裁判例に真っ向から反する結果になる上、かえって財産犯の成立範囲が広がる結論を招来するとも思われ、妥当とは思われません。
つまり、刑法総論と言う科目単体で見た場合は結果無価値論のほうが理論の一貫性、また客観的要素を重視して刑法と道徳倫理との過剰な混同(これが行き過ぎると、戦前の不敬罪のような犯罪の出現を招くことになる)を防ぐという意味において優れているとも見られますが、刑法各論や刑事訴訟法、また民法などの他の科目との整合性を考える場合には、やはり行為無価値論のほうが学習しやすいと思われるのです。
行為無価値論のメリットは、1.構成要件、2.違法性、3.責任という検討の中で、1番目の構成要件の検討の段階で「行為・結果・因果関係」という構成要件の客観面だけでなく「故意・過失」も構成要件の主観面として検討することになるので、刑法総論の重要な論点の大部分を構成要件の段階において検討することになるところです。結果として、2番目の違法性においては正当防衛や緊急避難等、刑法35条から37条の違法性阻却事由のみを検討すれば足りることになり、3番目の責任においては責任能力等、刑法39条以下の責任能力を検討すれば足りることになります。
語弊を生む可能性を承知でわかりやすく言えば、1番目の構成要件の検討を終えた段階ですでに犯罪成立に8割方近づいており、残り2割を違法性・責任で検討するような感覚になります。
これは、実際に答案を書く段階になってわかりますが、法律の世界によくある「原則・例外」パターンに近い感覚です。
構成要件の検討において犯罪が成立しそうかどうかの見通しがほぼつくわけです。ただ、最後に念のため違法性阻却事由の有無や責任阻却事由の有無を確認して例外的に犯罪不成立とならないかどうかを確認するという流れになりますので、文章として書きやすいです。
また、これは刑事訴訟法における主張・立証責任の所在ともリンクします。検察官は基本的に被告人が構成要件に該当する行為をしたことを証明すれば原則として有罪判決をとることができ、違法性阻却事由や責任阻却事由がある場合は被告人・弁護人から主張せねばならない(最終的な立証責任は検察官にあるが、被告人・弁護人からの主張は必要)という構造ともよく適合します。
したがって、刑法総論の学説としては結果無価値論が優勢なようにも思われますが(実際に書店で基本書を立ち読みすると結果無価値論の本が多いですね)、受験・実務に臨むのであれば行為無価値論のほうが優れていると思われます。
行為無価値論の欠点としてよく言われるのが、構成要件や違法性の検討において主観的な要素、ひいては倫理的な要素が入り込むことになり、理論的な精緻さを欠くという批判です。
たしかに行為無価値論の基本書の代表格である大谷實教授の『刑法総論講義』を読むと、重要な論点のほとんどで「社会的相当性」という、法律の条文にもなく内容もやや曖昧な言葉を用いて結論を導いているところが多いですが、この「社会的相当性」が、特に旧司法試験の時代には「マジックワード」(それさえ書いておけば何とかなるという理由で安易に使われる言葉を皮肉に評したもの)とされており、受験生からの評価も高くはありませんでした。
しかし、昔の司法試験では「○○説でなければ書けない」と言われるような問題が出題されたこともあったと聞きますが(実際に○○説でないと書けなかったかどうかまでは定かではありませんが)、今の司法試験はそこまでを求めていないはずです。
旧司法試験のように一つの論点について厚く学説を検討させるような問題はなくなり、学説を覚えていることよりも、比較的長文の問題から論点を抽出して要領よく結論を出すことが求められています。旧司法試験の末期(平成15年前後)からは既にそういう流れがありました。
したがって、司法試験も今や細かい論証で差をつけるようなかたちの試験ではなくなっていると思われますので、受験及び初心者向け学習に限った話ではありますが、行為無価値論の優勢は揺らぐところがないと思われます。
基本書を読む際に、受験生が突き当たる問題が「行為無価値論の本を読むか、結果無価値論の本を読むか」ということです。
刑法学者によって、行為無価値論をとる人もいますし、結果無価値論をとる人もいます。
勿論、学説の相違自体は他のどんな科目にもあることであり、それぞれの学説の論拠を調べてどの学説が最も相応しいと思われるかということを考えるのが法律学習の重要な部分なのですが、刑法総論の行為無価値論と結果無価値論の違いは、一つの論点に留まらず刑法総論全体の理解の違いに結びついてきますので、受験生を悩ませることになります。
行為無価値論は、違法性の本質を、犯罪の行為に重点を置いて解釈する考え方です。
殺人罪であれば、人を殺害するという行為が違法の本質ということになります。
結果無価値論は、違法性の本質を、犯罪の結果に重点を置いて解釈する考え方です。
殺人罪であれば、人を死亡させたという結果が違法の本質ということになります。
両説の最大の違いは、故意・過失の検討をどの段階で行うかということに繋がります。
刑法総論においては「1.構成要件 2.違法 3.責任」の順で犯罪成立の有無を検討することになりますが、故意・過失をどの段階で検討するかの位置づけが各説によって異なります。
行為無価値論であれば、1番目の構成要件の段階で故意・過失を検討します。
結果無価値論であれば、3番目の責任の段階で故意・過失を検討します。結果無価値論は、構成要件や違法性をなるべく客観的に(つまり、人の心情であるとか主観的なことを介入させずに)理解しようとするので、3番目の責任の段階にて故意・過失を検討することになります。
ただ、司法試験等の受験を意識するのであれば行為無価値論のほうが良いと思います。
結果無価値論のデメリットの一つは、刑法総論以外の科目との整合性の問題です。
結果無価値論は、構成要件と違法の段階では主観的な要素(つまり人間の心情のような要素)を排除しようとするところが特徴ですが、刑法各論においては、例えば財産犯の検討において「不法領得の意思」という主観的要素を検討します。最初から構成要件の検討において主観的な要素が入り込むことを否定しない行為無価値論においては故意に追加して「不法領得の意思」を検討することについて違和感はないですが、構成要件と違法性において主観的な要素が入り込むことを否定しようとする結果無価値論において「不法領得の意思」を検討することについては強い違和感があります。
この点、例えば結果無価値論である林幹人教授は『刑法各論』(第2版)において「実質的に重大な法益侵害に向けられた意思を犯罪成立要件と解するほかないであろう」(193頁)と記述しておられますが、その「犯罪成立要件」が刑法総論においてどのような位置づけになってくるのか不明確であるという印象を受けます。
同じく結果無価値論の曽根威彦教授は『刑法各論』(第4版)で不法領得の意思を不要としており、理論的には一貫していますが、最高裁判例に真っ向から反する結果になる上、かえって財産犯の成立範囲が広がる結論を招来するとも思われ、妥当とは思われません。
つまり、刑法総論と言う科目単体で見た場合は結果無価値論のほうが理論の一貫性、また客観的要素を重視して刑法と道徳倫理との過剰な混同(これが行き過ぎると、戦前の不敬罪のような犯罪の出現を招くことになる)を防ぐという意味において優れているとも見られますが、刑法各論や刑事訴訟法、また民法などの他の科目との整合性を考える場合には、やはり行為無価値論のほうが学習しやすいと思われるのです。
行為無価値論のメリットは、1.構成要件、2.違法性、3.責任という検討の中で、1番目の構成要件の検討の段階で「行為・結果・因果関係」という構成要件の客観面だけでなく「故意・過失」も構成要件の主観面として検討することになるので、刑法総論の重要な論点の大部分を構成要件の段階において検討することになるところです。結果として、2番目の違法性においては正当防衛や緊急避難等、刑法35条から37条の違法性阻却事由のみを検討すれば足りることになり、3番目の責任においては責任能力等、刑法39条以下の責任能力を検討すれば足りることになります。
語弊を生む可能性を承知でわかりやすく言えば、1番目の構成要件の検討を終えた段階ですでに犯罪成立に8割方近づいており、残り2割を違法性・責任で検討するような感覚になります。
これは、実際に答案を書く段階になってわかりますが、法律の世界によくある「原則・例外」パターンに近い感覚です。
構成要件の検討において犯罪が成立しそうかどうかの見通しがほぼつくわけです。ただ、最後に念のため違法性阻却事由の有無や責任阻却事由の有無を確認して例外的に犯罪不成立とならないかどうかを確認するという流れになりますので、文章として書きやすいです。
また、これは刑事訴訟法における主張・立証責任の所在ともリンクします。検察官は基本的に被告人が構成要件に該当する行為をしたことを証明すれば原則として有罪判決をとることができ、違法性阻却事由や責任阻却事由がある場合は被告人・弁護人から主張せねばならない(最終的な立証責任は検察官にあるが、被告人・弁護人からの主張は必要)という構造ともよく適合します。
したがって、刑法総論の学説としては結果無価値論が優勢なようにも思われますが(実際に書店で基本書を立ち読みすると結果無価値論の本が多いですね)、受験・実務に臨むのであれば行為無価値論のほうが優れていると思われます。
行為無価値論の欠点としてよく言われるのが、構成要件や違法性の検討において主観的な要素、ひいては倫理的な要素が入り込むことになり、理論的な精緻さを欠くという批判です。
たしかに行為無価値論の基本書の代表格である大谷實教授の『刑法総論講義』を読むと、重要な論点のほとんどで「社会的相当性」という、法律の条文にもなく内容もやや曖昧な言葉を用いて結論を導いているところが多いですが、この「社会的相当性」が、特に旧司法試験の時代には「マジックワード」(それさえ書いておけば何とかなるという理由で安易に使われる言葉を皮肉に評したもの)とされており、受験生からの評価も高くはありませんでした。
しかし、昔の司法試験では「○○説でなければ書けない」と言われるような問題が出題されたこともあったと聞きますが(実際に○○説でないと書けなかったかどうかまでは定かではありませんが)、今の司法試験はそこまでを求めていないはずです。
旧司法試験のように一つの論点について厚く学説を検討させるような問題はなくなり、学説を覚えていることよりも、比較的長文の問題から論点を抽出して要領よく結論を出すことが求められています。旧司法試験の末期(平成15年前後)からは既にそういう流れがありました。
したがって、司法試験も今や細かい論証で差をつけるようなかたちの試験ではなくなっていると思われますので、受験及び初心者向け学習に限った話ではありますが、行為無価値論の優勢は揺らぐところがないと思われます。
結果無価値論に対する疑問
結果無価値論に対する疑問点を、以下に若干記します。
結果無価値論は、大づかみに言えば、刑法の目的は法益の保護にあるとし、法益の侵害またはその危険(つまり、良くない結果が発生すること)を違法性の本質と解する見解です。
結果無価値論によれば、故意・過失という意志的要素は(同じ結果が発生するのであれば故意であろうが過失であろうが法益の侵害には変わりがないわけですから)違法性の本質に含まれず責任の問題に過ぎないことになり、また主観的違法要素も例外的な扱いとなります。
結果無価値論からの行為無価値論に対する主な批判は、(結果ではなく)行為の反倫理性までも違法の本質とし処罰の対象に含めるという行為無価値論の考え方は処罰範囲を不明確にする、というものです。
ただ、法益とは何でしょうか。
殺人罪の場合は人の生命、窃盗罪の場合は人の財産。これはわかりやすいと思われます。
では例えば、わいせつ物頒布罪の場合はどうでしょうか。わいせつ物頒布罪の保護法益は、性的秩序ないし健全な性的風俗(文化?)とされています。ですから、わいせつ物が頒布されれば、それが限られた空間での取引にとどまり、不快と感じる人がいなくとも、配布者は罪に問われるのです。
しかし、法益を「性的秩序ないし健全な性的風俗」というレベルにまで薄めるのだとすれば、それは結局判断の基準に、その侵害が反倫理的であるかどうかを取り込んでいることに他ならないのではないでしょうか。つまり、法益を、物理的・財産的な侵害に限らず、薄めに薄めて解釈することで、結局のところ、反倫理的行為そのものを処罰するのと異ならなくなるのではないかと思われるのです。例えば、現実にはあり得ない例ですが、「皇室を象徴とする日本国の善良な秩序」を保護法益に設定すれば、その法益を害する不敬罪も復活しうることになるのではないでしょうか。
もう一度わいせつ物頒布の例を挙げますが、自分の女性器を模して配布した「アーティスト」がわいせつ物頒布等で逮捕された事件がありましたが(裁判結果は未定)、他方で「かなまら」などの生殖器崇拝の宗教・文化を根絶しようという動きはありません。
これは一般的な感覚として不合理なことではなく、前者については多くの人がそれを正当な芸術と捉えていないのに対して、後者についてはそれが宗教行事・土着文化として、長い間、社会に広く認められているからだと思われます。しかし、性的表現としての程度や数量には差異はないはずです。
これは法益侵害説からはどう説明するのでしょうか。最終的には、社会がそれを許しているかどうかというところに帰結してしまうのではないかと思われます。
結局は、法益と言っても物理的・数量的に解釈しうるものばかりではなく、刑法各論の全類型の処罰根拠を説明しようとすれば、そこには必然的に一種の法的フィクションというか意思的な要素、倫理的な判断が入って来ることになると思われるのです。
もう一つ、特別刑法ですが「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」を例に挙げます。危険運転致傷、酩酊運転致傷、(通常の)過失運転致傷で、それぞれ刑の重さ(長期)が異なります。結果(法益侵害)としては、車の運転で人を怪我させたという点で同じです。ではなぜ刑の重さが異なるのでしょうか。無免許の場合には刑がさらに加重されますが、無免許であろうが何であろうが法益侵害の程度には違いはないのではないでしょうか。
この点、結果無価値論は、法益侵害の危険の程度が異なるから、という説明をするようです。無免許運転の場合は法益を害する危険の程度がより大きいから加重がなされるという説明のようです。しかし実際の事件において、危険性というのは「無免許だから」高まるというものではありません。無免許で国道のような一般道を時速20kmで走行している者よりは、免許有りでも住宅街の狭い一般道路を減速無し時速60kmで走行している者のほうが遥かに危険でしょう。無免許だから法益侵害の危険の程度がより大きいというのも、結局は一種のフィクションに過ぎないと思われるのです。
上記のような理由で、反倫理の観点を違法性の議論からほぼ完全に抜き取ってしまう結果無価値論の議論には今一つ違和感を覚えるところです。
これは別に調べて言うわけではありませんが、結果無価値論の根底には、近代的な唯物論や実存主義的な考え方があるのではないかと思うことがあります。
たしかに近代においては、神学・神に対する倫理に彩られた中世ヨーロッパ的思想からの脱却において、そうした論理はきわめて有用だったのかもしれないと思います。
かつて神格化された天皇を頂いた日本においてもそれは、もしかしたらある程度類推できる理屈だったかもしれないと思われます。
ただ、結果無価値を徹底させることは現行の刑法とどうしても矛盾を生ずるように思われるのです。
一弁護士如きが言えることではないですが、行為無価値が純粋行為無価値ではなくなり、結果無価値的な観点も取り入れた折衷的行為無価値論として生まれ変わった時点で、結果無価値論の歴史的な意義は果たされたのではないかと、思うこともあります。
刑法の基本書について
刑法総論の基本書について(2017年)
(この項の記述は古いものであるため、次の項の記述も併せてお読みください)
上記の通り、刑法総論について、司法試験対策としては、行為無価値論をとったほうが他の科目との整合性が取れるので良いと考えております。
それを前提として、刑法総論の基本書について、若干の感想を書きます。
試験用の基本書選択において大事なのは、司法試験で答案を書きやすいかどうかということです。
大学のゼミでの議論に勝つためには精密な議論をしている基本書のほうが良いのかもしれません。
しかし、司法試験の問題に時間内に回答する能力と、ゼミでの議論に打ち勝つ能力とは異なります。
司法試験(論文式)では教科書例題や判例そのままの問題は出ません。
大体、教科書例題や判例の事案を少しずらして、組み合わせたような問題が出ます。
その少しのずれや組み合わせに惑わされず、基本を守った立論ができるかどうかが問われます。
この点、判例が正当であるか否か、多数の文献を調べて追求していく学術的な議論とは異なります。
他の科目は大体が実務的なので、学術的な検討と司法試験の答案の差は出づらいのですが、刑法総論に関していえば理論的な側面が強いので、学術的な検討に役立つ基本書と司法試験で使える基本書に差があると考えています。
個人的には、今の時代でも、行為無価値論の基本書としては大谷實『刑法講義総論』が優れていると思います。
以前に書いたとおり、特に違法性について「社会倫理規範」「社会的相当性」「社会通念」という言葉が用いられており、大学のゼミにおける議論で勝つための材料となりうるかと言われると、わかりません。しかし、伝統的な構成要件・違法性・責任の枠組みを守っており、さらに理由づけも明快で理解しやすいのです。
明快で理解しやすいということは、それだけ司法試験において応用を利かせやすい(未知の問題にも対応しやすい)ということです。
たっぷりと時間をかけて多数の文献を調べられる状況であればともかく、有り合わせの基礎知識で素早く立論し、明快な記述を行う必要のある司法試験では、理由づけも明快で解りやすいものである必要があります。その意味ではこの基本書が現在も一番のお薦めです。
なお、仮に万が一結果無価値を取るとしたら、基本書は前田雅英『刑法総論講義』が良いと思います。
結果無価値論ではありますが、実務に適合するように修正が施されており、行為無価値論に思考の枠組みがよく似ています。
平成10年~平成15年ころのような勢いはないですし(当時は実務に即したあてはめ重視の前田説が非常に持て囃されていました)、総論・各論とも第6版でボリュームダウンしたのが残念ですが、判例紹介が豊富で、実務と大きくずれていない独自の結果無価値論です。学術的な点では批判も多いようですが、司法試験用の基本書としては今でも優れていると思います。
行為無価値論に話を戻します。今(2017)行為無価値論で人気があるとしたら、一つは高橋則夫『刑法総論』と思います。総論・各論が揃っているうえに記述が丁寧で説得的であるため、人気を博しているのだろうと思います。
ただ、司法試験対策に使うには難しい基本書かもしれません。序盤で「行為規範」「制裁規範」という法理学的な思考枠組みを紹介し、その後の理由づけにも「行為規範」「制裁規範」と言う言葉が多用されています。この「行為規範」「制裁規範」というのは明文上の用語でもなく、また団藤重光博士(戦後日本刑法学の大家)以降の刑法理論の中で伝統的に広く使われてきた用語でもありません。
司法試験の答案にいきなり「行為規範」「制裁規範」と書くわけにはいきませんから(仮に高橋説や規範の三分説を理解している採点者だったとしても字義を勝手に善意解釈できないため)、高橋説で答案を書くには「行為規範」「制裁規範」の用語から説明せざるを得なくなると思われます。
しかし短い試験時間でそのような余裕はないでしょう。その意味では、優れてはいるのかもしれませんが試験には使いづらいということになるかと思われます。
もう一つ、行為無価値で人気の基本書を上げるとしたら井田良『講義刑法学・総論』でしょうか。最近各論が出版されました。ただ、井田説も(少なくとも初版を読む限り)独特なところがあります。
例えば、行為論においては、現在では少数説とされている目的的行為論を採用しています。その他の異色な点としては、構成要件・違法性・責任の伝統的な枠組みで捉えておらず、違法性阻却事由を消極的構成要件要素としてとらえる考え方をとっています(誤想防衛の処理など、結論は同じでも立論において通説と相当の差異が生じます。同書351頁)。これを司法試験対策として見た場合、過失犯に関する答案を書く際に、前提として目的的行為論を取る場合の過失犯の処罰根拠を記述したり、答案で違法性に関する理由づけをする際に「違法性は独立した犯罪成立要件ではなく消極的構成要件要素であり」とひと手間余計にかけたりしなければならない、という欠点があるように思われます。
特に後者は、構成要件該当性は一般的・類型的な判断であり個別具体的な考慮を要しないという伝統的な枠組みに慣れた実務家にとっては、かなり難解に映ります。
私は、大谷實『刑法講義総論』以外の行為無価値論では、立石二六『刑法総論』が基本書としてわかりやすいという感想を持ちました。ややマイナーな基本書であり、通説ではない箇所も多数見られます(錯誤における数故意説を否定して一故意説、故意における制限故意説を否定して準故意説、緊急避難における二分説など)。しかし、学説を一つ一つ紹介したうえで私見で検討するという構成、また検討の際の理由づけが丁寧かつ明確な点が良いと思いました。
刑法各論の基本書がないこともあり、メインの基本書として使うには難しいかもしれませんが、行為無価値の立場からの立論のために補助的に使うには良いと思います。
ここまで「研究」ではなく「勉強」に絞った話を書いてきました。
司法試験対策とか実務的と言うことを言いすぎると、実務(判例や旧来の通説)べったりの思考は良くない、という批判もあるかもしれません。
たしかに、実務全面肯定で判例にも無批判、ということばかりでは刑法の体系的な理解に繋がりませんし、より良い刑法解釈のための議論は深まっていきません。司法試験対策のためではなく学術的に優れた基本書や評釈を読むことも当然必要であろうと思います。
ただ、少なくとも受験生には、一般的な実務家とも語り合うことの出来る、共通言語を持った基本書を使ってほしいとは思います。
受験生も、刑法ばかりやっているのではなく、刑法の後に刑事訴訟法を学んで、刑事裁判や刑事司法に関する議論の中で刑法理論をいかに使うかという段階に移行していくのです。
その各段階で純粋な刑法以外の議論に応用するために使える刑法理論となると、どうしても条文から大きく離れない、また実務家が長年親しんできた刑法理論の枠組みに基づいたものになるでしょう。
「行為規範」「制裁規範」と分類したり、違法性は独立した犯罪成立要件ではなく消極的構成要件要素であると位置づけたとしても実務家がそう簡単に理解しうるところではないはずです。
そして、前提となる共通言語がなくなってしまうと、結局は実務に対する影響も与えられないことになるのです。
Amazon含めインターネットの書評を見ると、刑法理論として精密に完成されているからこその高評価、というものがよく見受けられます。
しかし、研究者の著作として高く評価されるべき優れた基本書であるとしても、それが司法試験対策、また、その後の実務に向けて使いやすい基本書であるかどうかと言うこととはまた少し違うということです。
刑法総論の基本書について(2022年)初心者向け
2017年に前項を記述した後、しばらく基本書から遠ざかっておりました。
最近になって改めて書店の刑法の書棚を見ていて気付いたことがありました。
かつてのような重厚長大な基本書が少なくなっており、代わりに、「基本刑法Ⅰ・Ⅱ」や「リーガルクエスト」シリーズ、あるいは「日評ベーシック」シリーズに代表されるような、共著で、かつ、判例通説をベースにした内容の基本書が増えているという印象を受けました。
単独の学者の方が書かれた基本書もありますが、同じ学者の方が分量少なめの入門的な本を出されており、そちらのほうが存在感があるように見えました。
私が以前にこのホームページでお薦めした大谷實先生の『刑法総論講義』は見えず、また1990年代から2000年代における司法試験受験界において大谷實先生のライバル的存在だった前田雅英先生の書籍もかなり小さな扱いになっていました。
考えてみれば私が司法試験の受験勉強をしていたのは20年も前であり、刑法の基本書、刑法学習の世界にも世代交代が起きたということなのでしょう。
特に見たところ一番人気と思われる『基本刑法Ⅰ-総論』『基本刑法Ⅱ-各論』(大塚裕史・十河太朗・塩谷毅・豊田兼彦)は、司法試験学習に必要な詳しさは維持しつつ、判例・通説をベースに、少数説にも配慮しながら記述されているように思われます。
学者共著ではあるものの、かつての予備校本を意識した、ハイブリッド型のテキストという趣です。
行為無価値と結果無価値のいずれが良いという言及はありませんが、故意論・過失論を構成要件段階で検討しているので、通常の行為無価値論(正確には行為無価値・結果無価値二元論)をベースにしていることがわかります。
学生同士で、論点ごとにどの学説がいいのか、などということを熱く議論していた時代は過去のものとなったようです。
一抹の寂しさを覚えますが、今は判例・通説の思考ルートをたどって問題を素早く明快に解決する能力を高めることを優先したテキストのほうが主流になってきたのであろうと思います(既に以前からその流れはあったのであろうと思いますが、書店の品揃えを見て実感したのは初めてでした)。
今後は当分『基本刑法Ⅰ・Ⅱ』の時代が続くであろうと思います。
ただ、分量が厚いので、入門用としては、別の薄い基本書を読んだほうが良いと思います。
刑法総論の基本書について(2022年)中級者以上向け
ここで「中級者」と書いているのは、刑法学の中級者という意味ではなく、あくまで学生の勉強する科目・司法試験科目としての「刑法」の中級者以上、という趣旨です。
刑法の初心者は、まずは重要論点について最低限の基本判例と通説で立論できるようになることが重要です。
他の項でも書いたとおり、典型論点について判例・通説でさっと論証し、事例に即したあてはめを行って簡単な答案を作成できるようになったら中級者といって良いかと思います。
なお、初心者から中級者に登る段階では、ある程度の暗記学習は、あって良いと思います(基本的な論点について論証の仕方を暗記するなど)。思考力を鍛えることは大事ですが暗記をしなくていいということではありません。
ただ、もし基本判例・通説の勉強が一通り完了して、さらに刑法を確実な得点源にしていきたいという場合は、基本判例と通説をひたすら繰り返すだけでは学習として不足します(そもそも単調で退屈するはずです)。
そのような時は、あえて、判例・通説とは異なる考え方の基本書を読んで、批判的に検討しながら読んでいくという方法も有効かと思われます。
これがなぜ有効かと言うと、判例・通説をより多面的に理解できるようになるためです。
いかに判例・通説が司法試験対策に有効であるとは言え、ただ無批判に暗記しようとするだけでは逆に理解は深まっていきません。
法学は「なぜそう考えるのか」を重視する論理の学問であり、刑法は特に、実務的な都合を離れた理論的思考力が求められる科目ですから、判例・通説の「信奉者」となって、何かのマニュアルを覚えるような学習方法ではなかなか思考力は伸びて行かないものです。
判例・通説の考え方を取っておらず、むしろ判例・通説を批判している箇所が多い基本書を読んで、「たしかに一理ある、しかし…」と、反駁しながら読んでいくわけです。
できれば、なぜその基本書の論理よりも判例・通説の論理のほうが適切と考えるのか、という思考過程をメモしながら読んでいくといいと思います。
判例・通説を丸暗記するのではなく、外から客観的に見て、批判的に検討してみたり、逆に判例・通説への批判に対する再反論を自分の頭の中で組んでみることで、判例・通説の考え方がなぜ適切なのか、ということを自分の中で筋道立てて説明することができるようになるわけです。
初心者がこの方法をとると、かえって批判的に検討すべき相手の少数説に引っ張られてしまって混乱する可能性がありますし、また、細かい議論で勝つのではなくて全体の大まかな理解を優先せねばならないところ、細かい議論で勝つことを重視してしまうようになります。
他の科目でもそうですが、論点によっては少数説で考えたほうが一見妥当な論点も存在します。ただ、その場合、また別の論点について妥当な解決を導くことができないということがあります。通説は全体のバランス・整合性において優れているからこそ通説なのです。
したがって、ある程度勉強が進んでからこのような方法で勉強するのが良いと思います。
どの基本書を選ぶかは各自の読みやすい本で良いと思います。
私の個人的なお薦めは、松宮孝明教授の以下の基本書です。
『刑法総論講義』[第5版補訂版](2018年・成文堂)
『刑法各論講義』[第5版](2018年・成文堂)
2018年以降は改版がないため、今では手に入りづらくなっていますし、評価の分かれうる基本書ですので、無理にお薦めするものではありません。
ただ、なぜお薦めするのかという理由を書かせていただきます。
松宮孝明教授の基本書は、違法性に関しては結果無価値論の考え方をとっておられます。
また、ドイツの刑法理論や判例をベースに、理論的かつ厳密な論理展開によって、日本の判例・通説を批判している箇所が多いという特徴があります。
私がこの基本書をお薦めする理由は、松宮教授が、重要な論点についても、曖昧な記述で逃げることなく、かつ実務や時代の趨勢におもねることもなく、理論的かつ精緻な検討を行った上で学説を展開しておられるからです。
論点に関する結論については、実務とかけ離れていたり、実務家からすると疑問を感じる箇所もあったりして、松宮教授の学説に賛同できない箇所も多いのです。
ただ、それだけにかえって、実務家の立場からも深く考えさせられるものがあり、名著だと思います。
各論点について、著者の論理展開や結論と「格闘」しながら勉強を進めていくことで、判例・通説の理解も一層進むのではないかと思われます。
以上、中級者以上の学生に向けて、一つの勉強法の御提案でした。
もちろん、ここまでしなくとも合格レベルに達することはできると思います。
しかし、もし単純に判例・通説を忠実にトレースするだけの学習に平板さ・単調さを感じた時は、試してみていただければと思います。