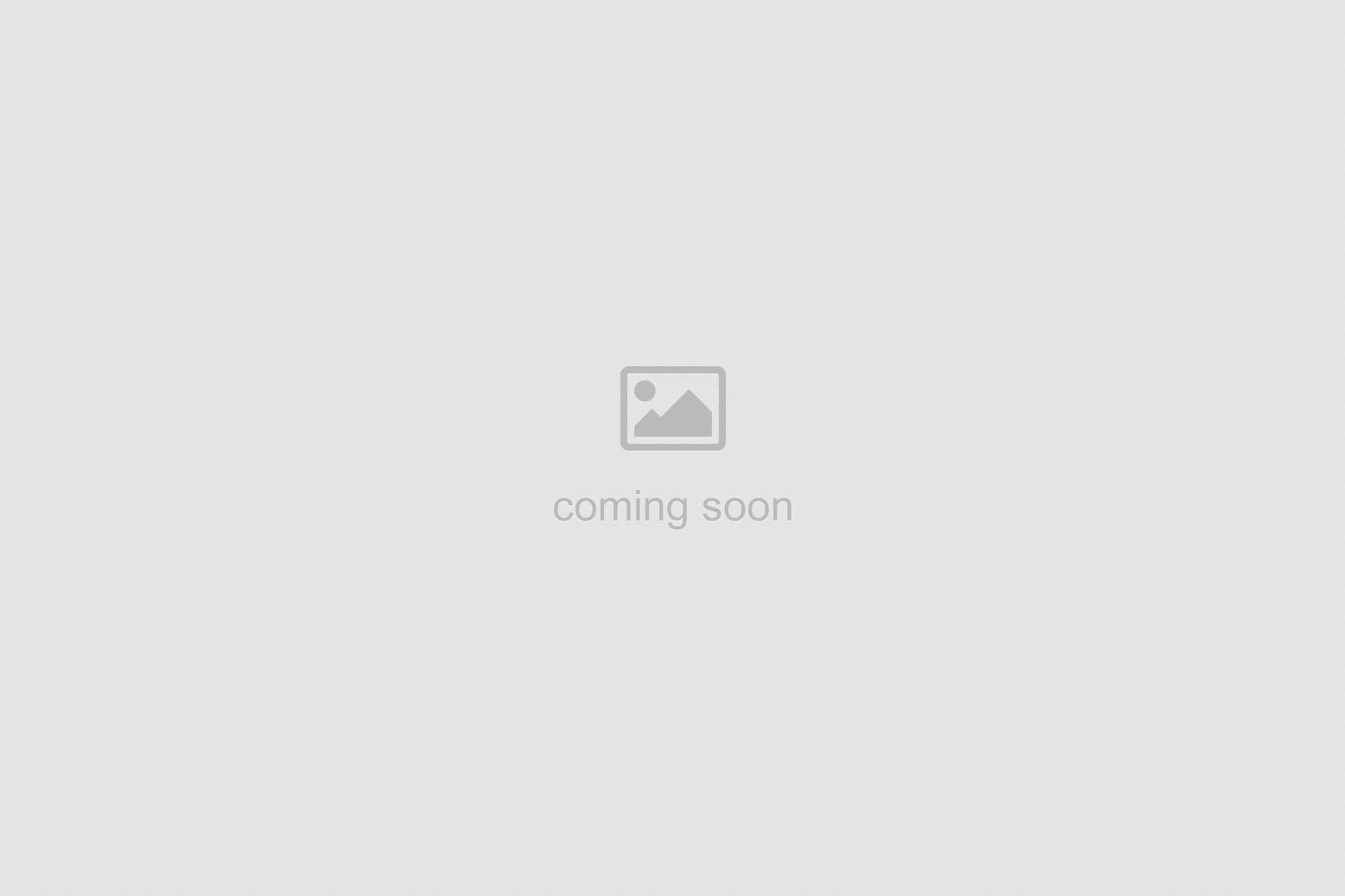構成要件論の概要
構成要件論の意義
刑法総論において最も重要になるのは構成要件論です。
構成要件とは,刑法の条文上に記載されている,犯罪が成立するための原則的な要件です。
例えば刑法235条の窃盗罪は「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」という条文になっていますが,この「他人の財物を窃取した」が構成要件になります。
もう少しマイナーな条文を探して例に取れば,例えば刑法147条の水道損壊及び閉塞の罪は「公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し,又は閉塞した者は,一年以上十年以下の懲役に処する」という条文になっています。
この条文では「公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し,又は閉塞した」が構成要件になります。
これが構成要件であるとすれば,ある行為が条文に書いてある構成要件に該当するかどうかを機械的に判断すればそれでいいのではないかと思われるかも知れません。
ただ,実社会では,境目な曖昧な,様々な行為が有り得ます。
例えば窃盗罪を例にとって考えてみます。
コンビニエンスストアの入口に傘立てがあり,雨の日に,ある客がその傘立てに白いビニール傘を預けて,店内で5分ほど雑誌の立ち読みと買い物をしてきたとします。
それで,店の外に出ようとすると,傘立てにある白いビニール傘が3本に増えていた。
勿論,自分の傘は1つだけで,ほか2つは他の客の傘に間違いないはずなのですが,何の特徴もない白いビニール傘なのでどれが誰の傘かわからない。
こういうときに,店内にいる他の客に直接声をかけて確認できる度胸のある人もなかなかいないでしょうから,大抵の人は,他の客が別の傘を持っていくまで待つか,あるいは,持った感じなどで「多分,これが自分の傘だろう」というものを選んでそのままさしていくのが通常ではないでしょうか(一番良いのは,予め見分けが付くようにラベルか何かを傘に張っておくことでしょうけれども)。
それで,電車の時間も迫っていたので,とりあえず「多分この傘が自分のものだろう」というのを選び取って,その傘をさして店を出たとする。
そのまま自分の傘だと思って持って帰ってきたものの,家に帰ってよく確認したら,やっぱり自分の傘ではなかったことに気づいたとする。
この場合,窃盗罪が成立するでしょうか。
もし仮にこれで窃盗罪が成立してしまうとすると,けっこうな数の人に窃盗罪が成立してしまう帰結になるかもしれません。
このように,窃盗罪という,本来シンプルなはずの犯罪類型でも,突き詰めていくと,犯罪成立としていいのかどうか迷うような事例が出てきます。
こういった問題について,どこまでが犯罪にならないのか、またどこからが犯罪になるのかを検討するのが刑法という科目です。
特に構成要件論については,この境目がどこまでなのかを突き詰めて考えることになります。
人によっては「そんなに突き詰めて考えなくても,その時その時で妥当な判断をすればいいんじゃないの」という感想をお持ちの方をおられるかもしれません。
しかし,例えば見るからに善良そうなAさんは犯罪不成立(無罪)と判断されたのにBさんは何となく悪そうなので処罰されたというのでは法の公平性を害することになります。
また,昨日は何のおとがめもなしだったのに,今日はいきなり逮捕されました,と言うのでは,これも法の安定性を害し,国民はかえって安心して生活ができないことになります。
それゆえ,一般的に見れば些細なことであっても,刑法を学習する上では突き詰めて考えていかなければならない,ということになります。
構成要件とは,刑法の条文上に記載されている,犯罪が成立するための原則的な要件です。
例えば刑法235条の窃盗罪は「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」という条文になっていますが,この「他人の財物を窃取した」が構成要件になります。
もう少しマイナーな条文を探して例に取れば,例えば刑法147条の水道損壊及び閉塞の罪は「公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し,又は閉塞した者は,一年以上十年以下の懲役に処する」という条文になっています。
この条文では「公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し,又は閉塞した」が構成要件になります。
これが構成要件であるとすれば,ある行為が条文に書いてある構成要件に該当するかどうかを機械的に判断すればそれでいいのではないかと思われるかも知れません。
ただ,実社会では,境目な曖昧な,様々な行為が有り得ます。
例えば窃盗罪を例にとって考えてみます。
コンビニエンスストアの入口に傘立てがあり,雨の日に,ある客がその傘立てに白いビニール傘を預けて,店内で5分ほど雑誌の立ち読みと買い物をしてきたとします。
それで,店の外に出ようとすると,傘立てにある白いビニール傘が3本に増えていた。
勿論,自分の傘は1つだけで,ほか2つは他の客の傘に間違いないはずなのですが,何の特徴もない白いビニール傘なのでどれが誰の傘かわからない。
こういうときに,店内にいる他の客に直接声をかけて確認できる度胸のある人もなかなかいないでしょうから,大抵の人は,他の客が別の傘を持っていくまで待つか,あるいは,持った感じなどで「多分,これが自分の傘だろう」というものを選んでそのままさしていくのが通常ではないでしょうか(一番良いのは,予め見分けが付くようにラベルか何かを傘に張っておくことでしょうけれども)。
それで,電車の時間も迫っていたので,とりあえず「多分この傘が自分のものだろう」というのを選び取って,その傘をさして店を出たとする。
そのまま自分の傘だと思って持って帰ってきたものの,家に帰ってよく確認したら,やっぱり自分の傘ではなかったことに気づいたとする。
この場合,窃盗罪が成立するでしょうか。
もし仮にこれで窃盗罪が成立してしまうとすると,けっこうな数の人に窃盗罪が成立してしまう帰結になるかもしれません。
このように,窃盗罪という,本来シンプルなはずの犯罪類型でも,突き詰めていくと,犯罪成立としていいのかどうか迷うような事例が出てきます。
こういった問題について,どこまでが犯罪にならないのか、またどこからが犯罪になるのかを検討するのが刑法という科目です。
特に構成要件論については,この境目がどこまでなのかを突き詰めて考えることになります。
人によっては「そんなに突き詰めて考えなくても,その時その時で妥当な判断をすればいいんじゃないの」という感想をお持ちの方をおられるかもしれません。
しかし,例えば見るからに善良そうなAさんは犯罪不成立(無罪)と判断されたのにBさんは何となく悪そうなので処罰されたというのでは法の公平性を害することになります。
また,昨日は何のおとがめもなしだったのに,今日はいきなり逮捕されました,と言うのでは,これも法の安定性を害し,国民はかえって安心して生活ができないことになります。
それゆえ,一般的に見れば些細なことであっても,刑法を学習する上では突き詰めて考えていかなければならない,ということになります。
構成要件論の内容
窃盗罪や殺人罪,あるいは文書偽造罪など,各個の犯罪類型ごとに生じる論点については「刑法各論」で学ぶことになります。
「刑法総論」の構成要件論では,(「総論」ですので)どの犯罪類型にも共通する(共通して存在しなくてはならない)要件について学ぶことになります。
分類すると客観的要素としては「行為」「結果」「因果関係」,主観的要素としては「故意」「過失」です。
なお,刑法総論に言う「客観」というのは,第三者からも感得可能な「表に現れている」ということ,「主観」というのは第三者からは感得不可能な「心の内にある」ということと,何となく理解していただければ,ここでは結構です。
民事訴訟法で出てくる主観・客観とは異なりますので初心者の方は注意して下さい。
このうち,実務上も,司法試験の上でも最も問題になるのは「故意」「過失」です。
前の項で挙げたようなコンビニエンスストアの傘立ての事例では,まさに故意(わざと)か過失(うっかり)かが問題になります。
次点は「因果関係」です。
刑事弁護人として実務に携わる中でも,たまに問題になるような事例に出会います。
「行為」「結果」が,刑法総論の構成要件のレベルで問題になることはあまり多くありません。
もちろん,ある行為がどの類型に該当するか(例:詐欺か横領か背任か)という問題が生じることはありますが,それは刑法各論の問題ですし,ある行為や結果が本当に存在したか否かという事実の真否が問題になることは非常に多いですが,それは刑事訴訟法の問題です。
刑法総論の基本書を読むと,この部分について「不作為犯」という論点と「間接正犯」という論点について多くの記述量を割いています。
刑法総論に対する理解を深めるためにはいずれも重要な論点と言えますが,しかし実務的にはかなりのレアケースです。
特に「間接正犯」は,後に出てくる「責任」概念を勉強していないと,なかなかスムーズに理解できないところではないかと思います。
したがって,「不作為犯」と「間接正犯」についてはざっと概観するにとどめて,客観的要素では「因果関係」,主観的要素では「故意」「過失」という,理論上も実務上も重要な点について,やや厚めに解説していきたいと思います。
「刑法総論」の構成要件論では,(「総論」ですので)どの犯罪類型にも共通する(共通して存在しなくてはならない)要件について学ぶことになります。
分類すると客観的要素としては「行為」「結果」「因果関係」,主観的要素としては「故意」「過失」です。
なお,刑法総論に言う「客観」というのは,第三者からも感得可能な「表に現れている」ということ,「主観」というのは第三者からは感得不可能な「心の内にある」ということと,何となく理解していただければ,ここでは結構です。
民事訴訟法で出てくる主観・客観とは異なりますので初心者の方は注意して下さい。
このうち,実務上も,司法試験の上でも最も問題になるのは「故意」「過失」です。
前の項で挙げたようなコンビニエンスストアの傘立ての事例では,まさに故意(わざと)か過失(うっかり)かが問題になります。
次点は「因果関係」です。
刑事弁護人として実務に携わる中でも,たまに問題になるような事例に出会います。
「行為」「結果」が,刑法総論の構成要件のレベルで問題になることはあまり多くありません。
もちろん,ある行為がどの類型に該当するか(例:詐欺か横領か背任か)という問題が生じることはありますが,それは刑法各論の問題ですし,ある行為や結果が本当に存在したか否かという事実の真否が問題になることは非常に多いですが,それは刑事訴訟法の問題です。
刑法総論の基本書を読むと,この部分について「不作為犯」という論点と「間接正犯」という論点について多くの記述量を割いています。
刑法総論に対する理解を深めるためにはいずれも重要な論点と言えますが,しかし実務的にはかなりのレアケースです。
特に「間接正犯」は,後に出てくる「責任」概念を勉強していないと,なかなかスムーズに理解できないところではないかと思います。
したがって,「不作為犯」と「間接正犯」についてはざっと概観するにとどめて,客観的要素では「因果関係」,主観的要素では「故意」「過失」という,理論上も実務上も重要な点について,やや厚めに解説していきたいと思います。
因果関係
因果関係論のポイント
因果関係というのは,ある行為があったためにその結果が生じたと言えるかどうかという問題です。
大抵の事例では,因果関係が問題となることはそう多くありません。
例えば,ある書店から本を万引きしたために,書店には財産的な被害が生じた。
これは当たり前ですね。
例えば,人を殴ったために,殴られた人が怪我をした。
これも当たり前ですね。
では,このような場合はどうでしょうか。
Aが口論の末にBを殴ったところ,Bはほとんど怪我を負わなかったが救急車を呼んだ。Bが救急車に乗せられて病院に運ばれる途中,救急車が交通事故に遭ってしまい,事故の衝撃で頭を打ったBは打ち所が悪く死亡した。
このような場合に,AがBを殴ったためにBが死亡したと言えるでしょうか。
たしかに「AがBを殴らなければBは救急車を呼ぶこともそれで運ばれることもなかったし,事故に遭うこともなかった。したがってAが殴ったためにBが死亡したと言える」という考え方もあるでしょう。Bの立場であればそう言いたくなるかもしれません。
しかし,客観的に見れば,さすがにAに,Bの死亡の結果にまで責任を負わせるのは酷でしょう。
普通の傷害罪(罰金で済むこともある)と傷害致死罪(3年以上の懲役)では刑の重さが異なります。
そこで,このような場合に,偶然的に生じた結果を排除する(行為者に責任を負わせない)ための論理として編み出されたのが「因果関係」です。
因果関係は,条文上に明確に規定されている概念ではありません。
したがって,「因果関係」の判断基底と判断基準をどのように考えるかについては諸説が分かれていて,この点については刑法の基本書ではそこそこの分量を割いています。
詳しい解説は各基本書を読んでいただければと思いますが,基本書の解説はなかなか複雑です。
基本書を読んでもわからないという方のために,ごくごく大雑把に言えば,因果関係論では「偶然的な結果を排除できればそれで良い」のです。
そして,偶然かどうかということは,法律の専門的な知識がなくても,一般的に判断できることです。
したがって,基本的には,因果関係は,「行為当時に一般人が認識し得た事情を判断基底として,一般人から見てそのような結果が生じるのが常識的に見て相当(偶然ではない)と言えるかどうか」で判断すべきであるということになります。
あくまで一般人基準で偶然かどうかを判断するのが,基本的なあり方です。
ただ,その場合に,行為者自身が認識していた事情を判断基底に含めないとすると問題も生じます。
例えば,Dが少し叩かれただけでも死亡する特殊体質で,Cがそれを知りながらDを殴打してDが死亡したという場合はどうでしょうか。
一般人からすればDがそんな特殊体質であることはわからないわけですし,少し殴打しただけで死亡するのは常識的に見て相当のことではないので,因果関係なしという結論にもなってしまいそうです。
ただ,それでは妥当性を欠くことになるでしょう。
CはDが特殊体質であることを知っていたわけですから。
そこで,最終的には「行為当時に一般人が認識していた事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎として,一般人から見てそのような結果が生じるのが相当(偶然ではない)と言えるかどうか」で相当因果関係の有無を判断することになります(大谷實『刑法講義総論』が詳しいです)。
この立場を折衷説と言い,少なくとも私が受験勉強をした時代はこの説が通説でした。
ただ,因果関係は客観的構成要件要素であるはずなのに,そこに行為者の主観が混じり込むのは(行為無価値論的な立場であっても)何となく腑に落ちないという感覚もあるでしょう。
そこで,事例ごとに,「1.行為の危険性の大小 2.介在事情の偶然性の大小 3.介在事情の結果への寄与度」を総合的に判断しようという説も有力に唱えられています(前田雅英『刑法総論講義』が詳しいです)。
個人的には,従来の通説である相当因果関係説でもいいですが,前田雅英教授の説のほうが,近時の司法試験に見られる「あてはめ重視」の傾向を考慮すると優れているようにも思われます。
ただ,大事なことは,(刑法の先生方からは怒られるかも知れませんが)最初に述べた通り,因果関係論では「偶然の結果を排除できさえすればそれでいい」のです。
そして,ほとんどの事例では因果関係はあまり問題にはなりません。
銃で撃ったから死亡した(殺人罪),取引で騙したから財産的な被害が発生した(詐欺),いずれも当たり前のことです。
偶然的な結果を排除するためだけの議論ですから,行為無価値と結果無価値の対立ともあまり関係はありません。
立ち並ぶ学説に惑わされず,問題を解く際には「偶然的な結果と言えるかどうか」だけ考えるのが良いと思います。
偶然生じた結果で,その責任を行為者に負わせるのが酷であると思われる事例であれば,その場合だけ因果関係を検討すべきです。
その検討をする際に用いるのが相当因果関係の折衷説であろうが,前田雅英教授の説であろうが,最終的には常識的なセンスをもとに偶然かどうかを判断するわけですから(その理屈づけのための前置きに学説を用いるわけです),どの理屈を採用するかでそう大きな差は出ないはずです。
大抵の事例では,因果関係が問題となることはそう多くありません。
例えば,ある書店から本を万引きしたために,書店には財産的な被害が生じた。
これは当たり前ですね。
例えば,人を殴ったために,殴られた人が怪我をした。
これも当たり前ですね。
では,このような場合はどうでしょうか。
Aが口論の末にBを殴ったところ,Bはほとんど怪我を負わなかったが救急車を呼んだ。Bが救急車に乗せられて病院に運ばれる途中,救急車が交通事故に遭ってしまい,事故の衝撃で頭を打ったBは打ち所が悪く死亡した。
このような場合に,AがBを殴ったためにBが死亡したと言えるでしょうか。
たしかに「AがBを殴らなければBは救急車を呼ぶこともそれで運ばれることもなかったし,事故に遭うこともなかった。したがってAが殴ったためにBが死亡したと言える」という考え方もあるでしょう。Bの立場であればそう言いたくなるかもしれません。
しかし,客観的に見れば,さすがにAに,Bの死亡の結果にまで責任を負わせるのは酷でしょう。
普通の傷害罪(罰金で済むこともある)と傷害致死罪(3年以上の懲役)では刑の重さが異なります。
そこで,このような場合に,偶然的に生じた結果を排除する(行為者に責任を負わせない)ための論理として編み出されたのが「因果関係」です。
因果関係は,条文上に明確に規定されている概念ではありません。
したがって,「因果関係」の判断基底と判断基準をどのように考えるかについては諸説が分かれていて,この点については刑法の基本書ではそこそこの分量を割いています。
詳しい解説は各基本書を読んでいただければと思いますが,基本書の解説はなかなか複雑です。
基本書を読んでもわからないという方のために,ごくごく大雑把に言えば,因果関係論では「偶然的な結果を排除できればそれで良い」のです。
そして,偶然かどうかということは,法律の専門的な知識がなくても,一般的に判断できることです。
したがって,基本的には,因果関係は,「行為当時に一般人が認識し得た事情を判断基底として,一般人から見てそのような結果が生じるのが常識的に見て相当(偶然ではない)と言えるかどうか」で判断すべきであるということになります。
あくまで一般人基準で偶然かどうかを判断するのが,基本的なあり方です。
ただ,その場合に,行為者自身が認識していた事情を判断基底に含めないとすると問題も生じます。
例えば,Dが少し叩かれただけでも死亡する特殊体質で,Cがそれを知りながらDを殴打してDが死亡したという場合はどうでしょうか。
一般人からすればDがそんな特殊体質であることはわからないわけですし,少し殴打しただけで死亡するのは常識的に見て相当のことではないので,因果関係なしという結論にもなってしまいそうです。
ただ,それでは妥当性を欠くことになるでしょう。
CはDが特殊体質であることを知っていたわけですから。
そこで,最終的には「行為当時に一般人が認識していた事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎として,一般人から見てそのような結果が生じるのが相当(偶然ではない)と言えるかどうか」で相当因果関係の有無を判断することになります(大谷實『刑法講義総論』が詳しいです)。
この立場を折衷説と言い,少なくとも私が受験勉強をした時代はこの説が通説でした。
ただ,因果関係は客観的構成要件要素であるはずなのに,そこに行為者の主観が混じり込むのは(行為無価値論的な立場であっても)何となく腑に落ちないという感覚もあるでしょう。
そこで,事例ごとに,「1.行為の危険性の大小 2.介在事情の偶然性の大小 3.介在事情の結果への寄与度」を総合的に判断しようという説も有力に唱えられています(前田雅英『刑法総論講義』が詳しいです)。
個人的には,従来の通説である相当因果関係説でもいいですが,前田雅英教授の説のほうが,近時の司法試験に見られる「あてはめ重視」の傾向を考慮すると優れているようにも思われます。
ただ,大事なことは,(刑法の先生方からは怒られるかも知れませんが)最初に述べた通り,因果関係論では「偶然の結果を排除できさえすればそれでいい」のです。
そして,ほとんどの事例では因果関係はあまり問題にはなりません。
銃で撃ったから死亡した(殺人罪),取引で騙したから財産的な被害が発生した(詐欺),いずれも当たり前のことです。
偶然的な結果を排除するためだけの議論ですから,行為無価値と結果無価値の対立ともあまり関係はありません。
立ち並ぶ学説に惑わされず,問題を解く際には「偶然的な結果と言えるかどうか」だけ考えるのが良いと思います。
偶然生じた結果で,その責任を行為者に負わせるのが酷であると思われる事例であれば,その場合だけ因果関係を検討すべきです。
その検討をする際に用いるのが相当因果関係の折衷説であろうが,前田雅英教授の説であろうが,最終的には常識的なセンスをもとに偶然かどうかを判断するわけですから(その理屈づけのための前置きに学説を用いるわけです),どの理屈を採用するかでそう大きな差は出ないはずです。
事例で考える因果関係
では、具体的な事例を検討してみましょう。
刑法総論においては、判例の学習も大事ですが、自分でいろいろな事例を設定して検討してみることも重要です。
学習の段階では、結論は判例と違っていてもいいと思います。
重要なのは考え方のプロセスを身につけることです。
例えば、前項のAがBを殴ったという事例を少し変えて、以下のような事例だったらどうでしょうか。
例題1
会社員Aは、自社の忘年会終了後、ほろ酔い加減で年末の混雑した繁華街を歩いていた。
その時、Aは通行人Bと肩をぶつけてしまったがAは謝らなかったのでBが立腹してAを呼び止めた。
Aは、せっかくの良い気分を邪魔されたことに腹を立ててBに飛びかかって、強く手拳で殴った。
Bは、不意をつかれたこともあって、歩道に仰向けに転倒し、頭を強打した。
Bが起き上がらないので他の通行人が慌てて救急車を呼んだ。
Bの頭の怪我は、1時間以内に治療すれば命は助かるものであったが、繁華街およびその周辺は車で大混雑しており、救急車到達まで30分かかった。
Bは救急車に乗せられて搬送されたが、途中で救急車が渋滞の車と衝突事故を起こしてさらにタイムロスし、救急車が病院にたどり着いたのは受傷から2時間後であった。
Bは懸命の治療を受けたが、死亡した。
いかがでしょうか。
まず、従来の通説である相当因果関係の折衷説で検討してみましょう。
判断基底(判断の基礎)はどこまでか。
行為時に一般人が認識しえた・行為者が特に認識していた事情は
・ AがBに飛びかかって強く殴ったこと
・ 付近は年末の繁華街で大混雑していたこと
この2点です。
これを基礎に、Bの死亡がAの行為から生じるのが相当(偶然ではない)と言えるかどうかを検討しましょう。
人に飛びかかって強く殴れば、殴られた人が転倒して治療が大けがを負うことくらいは常識的には考えられ得ることです。
そして、治療が必要な大けがを負ったとして、救急車が到着するのが遅れることも、現場が年末の繁華街であることを考えれば常識的には考えられ得ることです。
したがって、本件においてAの行為からBの結果が生じることは常識的に見て相当(偶然ではない)ことと考えられます。
よって、この事例では因果関係を肯定して差し支えないと思われます。
なお、前田雅英教授の説で検討すれば、1.Aの行為の危険性は高く、2.介在事情(年末繁華街の渋滞・事故)はさほど異常な事態ではなく、3.介在事情がBの死亡に及ぼした影響はそう大きくはないと考えられることから、この説でも因果関係は肯定される結果になると思います。
もう一題やってみましょう。
例題2
Aは煙草を吸いながら道を歩いていたが、煙草を捨てるのが面倒だったので、塀の向こうにあるB宅の庭先に、まだ火の消えていない煙草をポイッと投げ捨てた。
とろこが、B宅では、寒い季節が終わったということで、使わなかった灯油缶が庭先に置かれていた。
その灯油缶のふたをBが閉め忘れていたため、灯油缶の中にAの煙草が入り、引火して炎上し、B宅の庭と自宅が全焼した。
これもそんなに難しく考える必要はないはずです。
他人の家の庭先に火の消えていない煙草を投げ込めば(判断の基礎)、何に引火するかはともかくとして、何らかの可燃物に引火する可能性があることは一般人であれば認識または予見しうるところです。
灯油が置いてあることはレアかもしれませんが、古新聞紙が置いてあるかもしれないし、芝生や雑草があればそれに引火するかもしれない。
ですから、Aのタバコのポイ捨てと出火・B宅全焼との間の因果関係は認められるという結論になるはずです。
ただ、Aはわざと出火させたわけではないですから、放火の罪よりは軽い失火の罪になるでしょう。
刑法総論においては、判例の学習も大事ですが、自分でいろいろな事例を設定して検討してみることも重要です。
学習の段階では、結論は判例と違っていてもいいと思います。
重要なのは考え方のプロセスを身につけることです。
例えば、前項のAがBを殴ったという事例を少し変えて、以下のような事例だったらどうでしょうか。
例題1
会社員Aは、自社の忘年会終了後、ほろ酔い加減で年末の混雑した繁華街を歩いていた。
その時、Aは通行人Bと肩をぶつけてしまったがAは謝らなかったのでBが立腹してAを呼び止めた。
Aは、せっかくの良い気分を邪魔されたことに腹を立ててBに飛びかかって、強く手拳で殴った。
Bは、不意をつかれたこともあって、歩道に仰向けに転倒し、頭を強打した。
Bが起き上がらないので他の通行人が慌てて救急車を呼んだ。
Bの頭の怪我は、1時間以内に治療すれば命は助かるものであったが、繁華街およびその周辺は車で大混雑しており、救急車到達まで30分かかった。
Bは救急車に乗せられて搬送されたが、途中で救急車が渋滞の車と衝突事故を起こしてさらにタイムロスし、救急車が病院にたどり着いたのは受傷から2時間後であった。
Bは懸命の治療を受けたが、死亡した。
いかがでしょうか。
まず、従来の通説である相当因果関係の折衷説で検討してみましょう。
判断基底(判断の基礎)はどこまでか。
行為時に一般人が認識しえた・行為者が特に認識していた事情は
・ AがBに飛びかかって強く殴ったこと
・ 付近は年末の繁華街で大混雑していたこと
この2点です。
これを基礎に、Bの死亡がAの行為から生じるのが相当(偶然ではない)と言えるかどうかを検討しましょう。
人に飛びかかって強く殴れば、殴られた人が転倒して治療が大けがを負うことくらいは常識的には考えられ得ることです。
そして、治療が必要な大けがを負ったとして、救急車が到着するのが遅れることも、現場が年末の繁華街であることを考えれば常識的には考えられ得ることです。
したがって、本件においてAの行為からBの結果が生じることは常識的に見て相当(偶然ではない)ことと考えられます。
よって、この事例では因果関係を肯定して差し支えないと思われます。
なお、前田雅英教授の説で検討すれば、1.Aの行為の危険性は高く、2.介在事情(年末繁華街の渋滞・事故)はさほど異常な事態ではなく、3.介在事情がBの死亡に及ぼした影響はそう大きくはないと考えられることから、この説でも因果関係は肯定される結果になると思います。
もう一題やってみましょう。
例題2
Aは煙草を吸いながら道を歩いていたが、煙草を捨てるのが面倒だったので、塀の向こうにあるB宅の庭先に、まだ火の消えていない煙草をポイッと投げ捨てた。
とろこが、B宅では、寒い季節が終わったということで、使わなかった灯油缶が庭先に置かれていた。
その灯油缶のふたをBが閉め忘れていたため、灯油缶の中にAの煙草が入り、引火して炎上し、B宅の庭と自宅が全焼した。
これもそんなに難しく考える必要はないはずです。
他人の家の庭先に火の消えていない煙草を投げ込めば(判断の基礎)、何に引火するかはともかくとして、何らかの可燃物に引火する可能性があることは一般人であれば認識または予見しうるところです。
灯油が置いてあることはレアかもしれませんが、古新聞紙が置いてあるかもしれないし、芝生や雑草があればそれに引火するかもしれない。
ですから、Aのタバコのポイ捨てと出火・B宅全焼との間の因果関係は認められるという結論になるはずです。
ただ、Aはわざと出火させたわけではないですから、放火の罪よりは軽い失火の罪になるでしょう。
故意
故意とは何か
客観的に構成要件に該当する行為を行っただけでは犯罪は成立しません。
例えば、他人の傘を自分の傘だと思い込んで持ち去った場合には、客観的には窃盗罪の構成要件に該当する行為を行ったことになりますが、それだけでは犯罪成立とはなりません。
その行為を「故意」をもって行ったことが窃盗罪成立のためには必要です。
では、故意とは何かということですが、平たく言えば自分の犯罪行為を認識しながら敢えてこれを行うこと、ということです。
もっと一般的に言えば「わざと」ということに近いですが、完全に同じ意味ではありません。
例えば、わざと人にぶつけようと思ってその人めがけて石を投げてぶつけた。
これは暴行罪の故意有りとなります。
では、自分の石投げの腕に自信があって、その人には石はぶつからないだろう、もしかしてぶつかるかもしれないがそれでもいい云々と考えて、その人の横30センチくらいの地面を狙って石を投げたが、予想に反してその人に石が当たってしまった、という場合はどうでしょうか。
「わざと石をぶつけた」わけではないから故意はないのでしょうか。
結論から言うとこの場合にも故意は認められます。
「わざと」と言うレベルまで行かなくても、自己の犯罪行為を認識しつつそれを行えば故意は成立するのです。上記の「ぶつかる(犯罪行為になる)かもしれないが、それでもいい」というレベルの主観的態様でも、故意は成立します。上記のような故意を、明らかに犯罪行為をしようとしていた場合(確定的故意)と区別して「未必の故意」と言います。
「未必の故意」はわかりにくい法律用語の代表格ですが、刑法学習の上では身に着けておく必要があります。
故意と刑事訴訟
刑法学を学び始めた時によくわからないのが、実際に故意の有無をどうやって確定するのかと言うところの疑問です。
処罰されたくないのなら「わざとじゃありませんでした」「そんなつもりは全くありませんでした」と言えば処罰されなくなったり、刑が(過失犯として)ずっと軽くなったりするのでしょうか。
これは,初学者であれば当然に行き当たる疑問かと思います。
ただ,実際の裁判では、故意の有無は、被告人本人の供述もさることながら、客観的な証拠から立証・反証することになります。
例えば、殺人事件の起きた際に、殺意(殺人の故意のことを「殺意」と言います。法曹もよく使いますが,実は法文上の用語ではありません)があったか否か。
「殺すつもりはなかった」という弁解は、現実の法廷ではなくても小説やドラマでもよく見られるところです。
では、殺人と、過失致死や傷害致死(傷つけたところその傷がもとで死亡した場合)との区別を、どのようにつけていくのでしょうか。
まず、現実にこうした事件で故意が問題になった場合は、使用した手段や、武器であればその形状が問題となることが多いと思われます。
素手で殴りつけたというだけでは殺意が認定される可能性は低いでしょう。他方で、刃物や鈍器など殺傷力のある武器を使用している場合は、殺意が認定される可能性は高まります。
同じ武器を使っていても、その使い方によって、また故意の認定は異なります。
鈍器を使用していても、傷・あざの場所が被害者の脚や腕にしかなければ、通常骨折等はすると思われますが死亡結果につながる可能性は低いので(もちろん度重なる打撃であれば充分に死亡可能性はありますが)、殺意が認定される可能性は低くなるでしょう。他方で、刃物を使って、胴体や動脈の通っている部分など人体の重要部分を斬りつけた場合は殺意が認定される可能性は高くなります。
このように、刑事裁判では故意(主観)の認定であっても、客観的な証拠が重視されます。
本人の証言(供述)と客観的な証拠が一致していれば信用性ありとされると思われますが、本人の証言(供述)と客観的な証拠が全く異なる場合は、信用性が否定されることになるでしょう。
単に本人が言い逃れさえすれば罪責が軽くなるというものではありません。
刑法上は主観的な構成要素と言っても、刑事裁判上においても主観的にのみ認定されるわけではありません。
この点は刑法の教科書に書かれている部分ではない(理論体系との関連が薄い)ので、念のため書き記します。
故意と錯誤論(具体的事実の錯誤)
故意について重要となるのが錯誤論です。
錯誤論とは、行為者自身の意図していなかった犯罪事実が発生した場合(意思と結果との間に食い違い=錯誤がある場合)に故意が認められるかどうかという議論です。
なお、故意と過失は別個のものですので、検討の結果として故意が否定されても過失が別個成立することは有り得ます。過失についてはいずれ項を改めて説明します。
錯誤の例としてよく挙げられる教科書事例は、闇夜でAを殺害しようとしてピストルを発射したところAだと思っていたのはBであり、Bが弾丸で死亡したという事例です(客体の錯誤)。また、Aを殺害しようとしてピストルを発射したところAの隣にいたBに弾丸が当たりBが死亡したという事例もあります(方法の錯誤)。
この場合に、行為者にBに対する殺人の故意を認めるか否か、学説が法定的符合説と具体的符合説に分かれます。
結論から言うと、現在は法定的符合説が優勢と考えていいと思います。
したがって学習の上ではあまり迷う必要がないところですが、具体的符合説も、故意とは何かを考える上では有用な学説ですので、その内容を把握しておくことは無駄ではありません。
具体的符合説というのは、「行為者はAを殺害しようとしていたのであってBを殺害しようとしていたわけではないのだから、行為者にBに対する殺人の故意があるとは言えず、Bに対する過失致死罪が成立する」というものです。
しかし、故意というのは、犯罪の意志のない行為を(過失が成立する場合を除いて)処罰しないために編み出された概念であるはずです。そうであれば、犯罪、つまり法(殺人の場合は刑法199条)に反する意思が行為者にあった以上は、故意の成立を認めて差し支えないというべきです。
実際、具体的符合説を取った場合、殺人の事例であるからまだ行為者にはBに対する過失致死罪が成立するとして処罰する事は一応可能ですが、これが人ではなく物だったらどうなるでしょうか。
たとえば彫像Aを壊そうとして彫像Bを壊してしまった場合、具体的符合説では、彫像Bに対する過失の器物損壊があったことになります。
しかし、過失の器物損壊を処罰する規定は現行法にありませんから行為者には何らの犯罪も成立しないことになります(前田雅英『刑法総論講義(第5版)』270頁に同旨の記述があります)。
具体的符合説は故意概念を考えるための一つの理論としては存在しますが、実務的には馴染みづらい学説と言えます。
そして、前述したように、Aを殺害するにしてもBを殺害するにしても同じ「殺人罪」の規範(人を殺してはならない)に直面して、これを乗り越えて犯罪を犯している点では変わりないわけですから、行為者にはBに対する殺人の故意が認められ、客体の錯誤・方法の錯誤いずれの場合でも殺人罪の成立を認めるのが法定的符合説であり、今日の通説です。
ただし、法定的符合説の間でも一故意説と数故意説の対立が存在しますので注意が必要です。
上記の事例で、Aを殺害するつもりで撃った弾丸がAとB両方に命中してAとB両方が死亡した場合を考えてみましょう。
法定的符合説の中でも一故意説は、故意としてはA1名を殺害するつもりであったのであるから、Aに対する殺人罪は成立するが、Bに対する殺人罪は成立しないとします(1名殺害の故意をAの罪責で使い切ったという考え方)。これに対して数故意説は、AとBいずれに対しても殺人既遂罪が成立するとします。
ここでは、数故意説が通説であることを覚えておけば良いと思います。
これも、教科書事例とは少し違う、「20名が出席する予定のパーティーに、その20名を殺害する意思で爆弾を投げ込んだら、実はパーティーには予定外の飛び入り客がいて21名が死亡した」という場合に、20名に対する殺人罪のみ認め、残り1名に対しては過失致死罪しか認めないというのは明らかに不合理です。
そもそも故意と言うのは上記の通り法律(規範)に違反するという認識のことであり、それを持たなかった(自分の犯罪を認識しなかった)者を処罰しないというための法律的概念ですから、数量化できるものではないと思われます。
したがって、上記例に挙げたような具体的事実の錯誤については、法定的符合説と数故意説をまずはマスターし、余裕があれば具体的符合説や法定的符合説の一故意説を学習すれば足りると思われます。