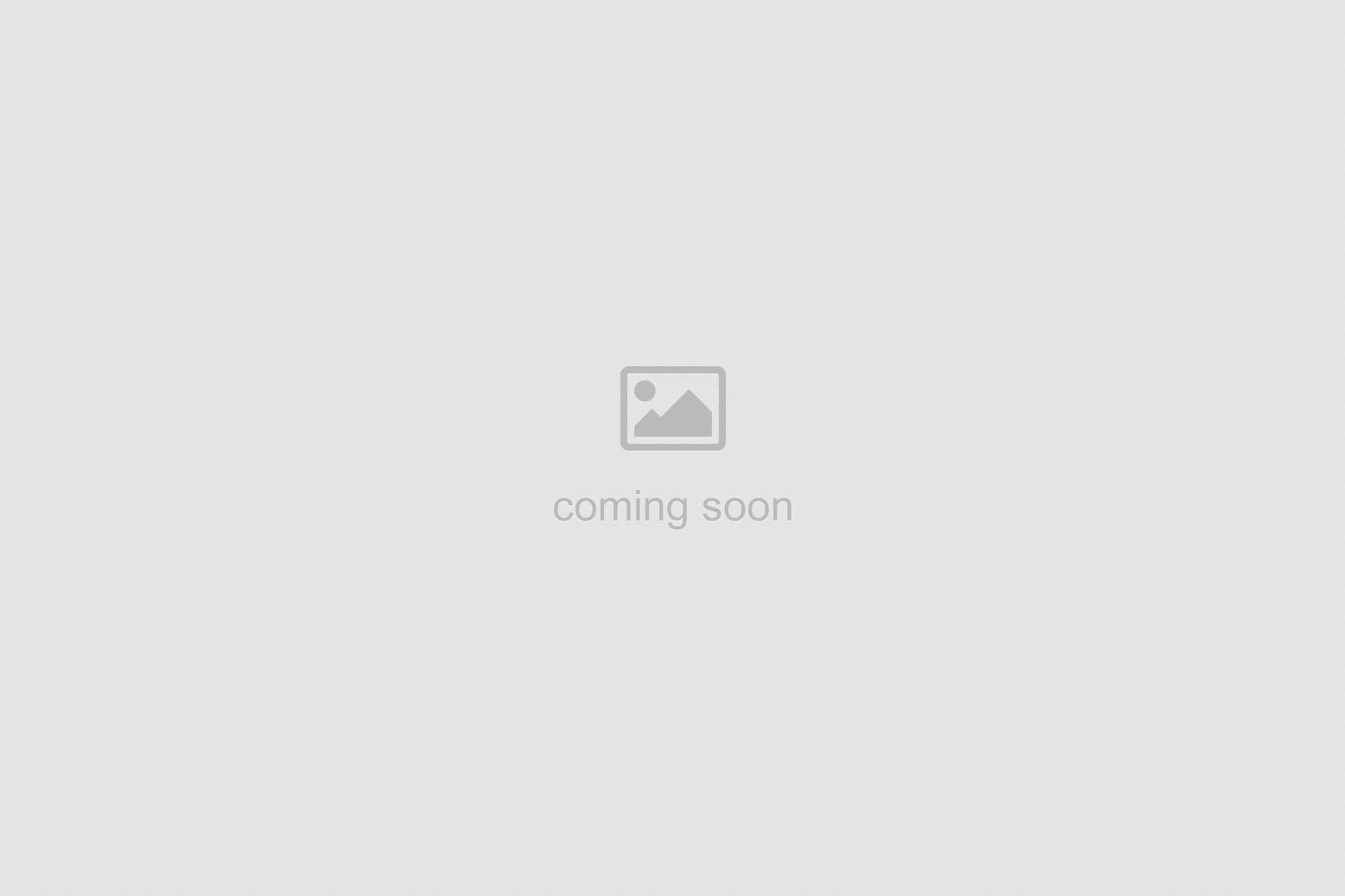民事訴訟と住所
住所と管轄
この訴状には、当事者(訴える者、訴えられる者)を記載します。
訴える者が原告、訴えられる者が被告です。
そして、原告、被告いずれについても住所の記載は必須です。
住所「不定」では基本的に訴訟は提起できませんし、また、住所「不定」の相手に対して訴訟を起こすことは原則的にはできません。
なお、「本籍」については、相続など家事事件では必要になることもありますが、一般の民事事件では原則必要ありません。
なぜ「住所」が必要なのか。
まず第1には管轄の問題があります。
民事訴訟法第4条は、被告の生活の根拠地の裁判所に管轄権を生じるとしています。
つまり、訴えたい相手(被告)が横浜にいる場合は横浜地方裁判所に、福岡にいる場合は福岡地方裁判所に訴訟を提起しなければならないということです。
生活の根拠地というのは基本的に住民票のある住所、住民票通りの場所にいないときには実際の居所を基準にして決まります。
居所というのも、「この辺にいる」では足りません。番地や部屋番号の特定まで必要です。
このように、管轄との関係で住所はどうしても必要になります。
なお、会社の場合は本社所在地の裁判所が基本的な管轄になります。
もちろん、被告の生活の根拠地や被告の事業所所在地でしか民事裁判が起こせないとなると種々の不都合が生じますので、民事訴訟法は、不法行為があった時はその不法行為地において裁判を起こせることを認めていますし、また、契約などの事件では義務履行地(契約に定められた義務が果たされるべき場所)に管轄を認めています。
これにより、例えば大阪から仙台に旅行に来たAが仙台市内で仙台在住のBを殴って弁償もせず帰って行った場合に、Bが殴られた損害賠償をAの住所である大阪地方裁判所に起こさなければならないという不都合を避けることができます。また、東京から仙台に仕事に来たCがD所有のマンションを数か月賃借したものの賃料を一切払わずに東京に帰ってしまった場合などに、東京地方裁判所に訴訟提起しなければならないという不都合を避けることができます(いずれも仙台地方裁判所に訴訟提起可能です)
なお、契約書上に「本件契約に関して紛争が生じた場合は〇〇地方裁判所を第一審の裁判所とする」と定められていることがあります。これは合意管轄と言います。仙台在住の人なのに第一審が東京地裁となっている契約書を締結してしまい東京に訴訟を提起されてしまうということもあるようですが、これはいずれ項を改めて説明することにします。
送達の問題
住所が要求されるのは管轄の問題だけではありません。
訴状の送達の関係で、住所(あるいは居所)は必須です。
裁判所には訴状を2通(正本、副本)提出します。
その正本は裁判所の記録に編綴され、副本は裁判所から被告に送達されます。
そして、被告が送達を受けた時に、初めて訴訟が動き出します。
これを、訴訟が「係属」したと言います。
基本的に送達は書留郵便で行われます。
したがって、郵便送付先の住所がわからないのでは送達は果たされないことになり、訴訟は開始しないことになります。
住所「不定」の相手に訴訟を提起したり、また「多分あの辺に住んでいる」で訴訟を提起したとしても(できませんが)、実質的には全く訴訟は開始しないことになります。
これを不便と感じる方も多いと思います。
しかし逆の(訴訟を起こされる側の)立場で考えてみれば、送達を経ないと訴訟が開始しないというシステムは被告側の手続保障にとって重要な役目を果たしていることになります。
例えば、どこの誰とも知れないAが、「宮城県仙台市のどこかにいる甲に対して100万円を貸しているから、それを返してくれ」という訴訟を仙台地方裁判所に提起して、甲が実際に仙台市のどこにいるかはわからないし訴状も送達されてないけど訴訟が始まってしまう、というのでは甲にとって大変です。
同じことを考えたBもCも同様の訴訟を甲に対して提起して、送達なしでA、B、Cが全員勝訴判決を得てしまったらどうなるでしょうか。甲は、全く何も知らないうちに100万円×3人分で300万円を支払わされることになり、これは到底妥当とは言えません。
被告の住所に訴状が送達されることで「あなたに対してこういう権利を主張している人がいますよ、あなたのほうで反論があれば反論してください」というシグナルになるわけです。
したがって、送達のためにも住所は必要になります。
消費者系事件との関係での教訓
1.怪しい業者には迂闊に住所を教えない。
最近は報道などにより対策が成熟してきた感はありますが、未だに「〇〇様、あなたに対して当社は50万円のサイト利用料を請求します。もし一週間以内に当社に連絡なき場合には訴訟提起・直接訪問等の措置をとります」というメールが届くことがあるようです。
2.事業所所在地がわからない業者を安易に信用しない。
最近はインターネットが普及し、多くの業者が業者紹介のHPを設置しています。
しかし、よく見ると会社所在地がハッキリしない業者というのもあります。
商品紹介等がやたら充実している割に、その業者の事業所所在地がハッキリしない、という場合は警戒したほうが良いと思われます。
もちろん、事業所所在地が明らかでありさえすればいいと言うものでもありません。
会社が登記の際に届け出ている事業所所在地に実際の業務の中心があるとは限りませんし、また、単にレンタルオフィスである可能性もあります。
実際に自分の目で事業所(きちんとした店舗やビル)を確認できる相手とのみやり取りするのが、最も確実です。
訴訟上の和解について
訴訟を起こしたのに和解?
ネット上の掲示板等で弁護士に関する不満・意見などを見ていくと,よく見られる不満に「弁護士に訴訟を依頼したのに和解を勧められて不信感をもった」というもの,あるいは「弁護士に勧められて和解したけど納得いかないので再度提訴しようと依頼したら無理だと言われた」というものがあります。
たしかに,徹底的に相手と戦うつもりで事件を依頼したのに,提訴したらいきなり裁判所から和解を打診された,自分の頼んだ弁護士も和解を勧めてきたけど,何で和解なんかしないといけないんだという感想を持たれる方もおられるかもしれません。
ただし,訴訟における和解は「訴訟上の和解」と言って,一般的な和解契約とはかなり法的な意味が異なるものです。
ここでは訴訟上の和解ということについてある程度詳しく解説します。
訴訟上の和解の効力
ここで「請求の放棄若しくは認諾」というのは,相手に対する請求権が無いことを全面的に認めるか(放棄),若しくは相手方が請求権について全く争わない(認諾・単純に認めるだけではなく支払延期であるとか分割払いであるとかも一切無し)ことを指しますので,実務上はレアケースです。
つまり重要なのは「和解を調書に記載したときは,その記載は,確定判決と同一の効力を有する」ということです。
確定判決は,それを根拠(債務名義)として,差押・競売等の強制執行をかけることができます。
例えば「AはBに金100万円を支払え」という確定判決であれば,その金100万円をBが支払ってこないときはBの所有する不動産や,得られるべき給与の一定割合を差し押さえることができます。確定判決というのは非常に強力な効果を有する文書です。
その確定判決と同じ効力を持つ文書を,和解―つまり双方の話し合いで―作成しうるわけです。
もちろん,判決と違って当事者双方の納得が必要なので,その点では確定判決と比べると相手に譲歩した内容になってしまいやすいのですが,一旦作成してしまえば,確定判決と同一の効力がありますので,それが破られた場合には確定判決と同じく強制執行できます。
訴訟ではない場所で示談・和解をしてもそこまでの効力は原則としてありません(公証役場で作成できる公正証書がほぼ唯一の例外です)。その示談・和解が守られないときはもう一度訴えを提起してさらにそれでも義務が果たされないなら強制執行をするほかありません。
効果の点で,訴訟上の和解と普通の和解は異なります。
極端な言い方をすれば,訴訟上の和解の内容がこちらにとって非常に有利なものであれば,それは実質的な勝訴判決と同視してよいということです。
訴訟上の和解のメリット
まず訴訟上の和解のメリットについて説明します。
一つは,不服申立制度がないことです。
一旦和解が成立すれば,それに対する不服申立はできません。和解の前提に重大な錯誤があった場合には理論上は和解の取消は可能とも言われますが,実務上は和解取消の事例というのはほとんどありません。
これに対して,あくまで相手と戦って判決をとるということを選んだ場合,仮に勝訴判決を得ても相手は高等裁判所に控訴することが出来ます。控訴の結果が不服であれば最高裁判所に上告をすることもできます。最後まで争った場合は上告棄却でようやく判決確定となるわけですが,そうなると判決確定までに時間がかかりすぎます。
仮執行宣言付判決を債務名義とする方法もありますが,これも執行停止の申立がされてしまうと執行できなくなります。
つまり,和解せずに判決をとった場合でも後でその判決が覆される可能性はあるし,また覆されないとしても時間と労力がかなりかかることになります。
一つは,原告側にとっては支払を得られる可能性が高まることです。
判決はある意味で強権的に被告の支払義務を決めるわけですから,被告とすれば当然精神的なわだかまりが残りやすいです。中には,元々払うつもりでいたのに,判決で命令されるのでは支払う気にならないという被告もいるかもしれません。勿論そんな言い分は法的には通用しないのですが,仮に不動産も収入もない被告が判決に記載された支払を拒否して逃げた場合は,お金の回収しようがありません。
被告を拘束できないのは訴訟上の和解の場合でも同じですが,訴訟上の和解の場合は被告としても自分の納得の上で和解しているわけですから,支払ってくれる可能性は相対的には高いと言えます。
もう一つ,「柔軟な取り決めが出来る」というのもメリットです。
判決の場合は,お金を幾ら支払えとか,不動産の所有権移転登記をせよとか,ある程度定型的な文言しか判決文に含めることは出来ません。分割払いを命じる判決というのも通常ありません。判決の場合は一括支払が前提です。訴訟上の和解であれば,「BはAに謝罪する」とか「AとBは本件訴訟の内容について口外しない」等の条項を盛り込むことも可能です。また,相手の了解が得られればですが,分割払いや,相当期間を延長しての支払も可能です。
そして,これは原告・被告双方にとっての話ですが,訴訟の勝ち負けというのは案外に見えづらい場合が多いと言うことです。
支払義務ある金額も明確に決まっていて,どんな判決がでるか(どちらが勝つか)わかりきっている事件もあります。
ただ,特に損害賠償・慰謝料請求の場合などは,果たしてどんな判決が出るか,原告・被告は勿論のこと,弁護士にもハッキリとはわかりません。単に従来の取扱や相場感覚からすればこのくらいの賠償義務かなという何となくの目星がつくだけのことです。
例えばAがBに慰謝料100万円の請求をした訴訟で,どのような判決が出るか分からない場合,裁判官は請求棄却するかもしれませんし,また請求を100%認めるかもしれません。また,一部を認めて40万円,50万円,60万円くらいに落ち着く可能性もあります。
こういったときに例えば50万円の支払ということで和解をすると,原告としては請求棄却されるという敗訴リスクを回避できますし,被告としては請求が100%認められるという敗訴のリスクを回避できます。
訴訟上の和解のデメリット
ただ,訴訟上の和解にいかにメリットがあるとは言っても「和解をしたくない」という方はおられると思います。
例えば,慰謝料請求の事案などで,お金ではなく相手方が二度とこういうことをしないように懲らしめたいという場合などです。
この場合でも,やはり訴訟上の和解にメリットがあることは間違いないので弁護士としては訴訟上の和解を勧めることが多いかと思いますが,それで最終的にどういう決断をするかは依頼者の方次第となります。
訴訟上の和解をするときの注意点
調書に記載するのは和解に立ち会った裁判官と裁判所書記官ですから,訴訟上の和解というのは当事者や代理人の署名押印を必要とせず,裁判官が当事者双方立ち会いのもとで和解条項を読み上げ,その場で裁判所書記官が調書に和解条項を記載した段階で効力が生じます。
この点は普通の和解契約との大きな違いであり,裁判所で当事者の方がよく驚かれるところです。
和解成立の後「もう終わりでいいんですか(署名や押印は要らないんですか)?」と質問されることがありますが,普通の和解契約と異なり,裁判官が和解条項を読み上げてそれに双方異議がなければそこで和解成立です。
したがって,訴訟上の和解をする時には事前に納得いくまで和解条項を当事者双方で詰める必要があります。
裁判官が読み上げる条項は「案」ではなくて,確定判決と同一の効力を有するという,強力な法的効果を有する文書ですから,よく検討した上で和解成立をさせることが大事です。
和解成立した後で異議を述べても,よほどのことがなければ通りません。
私の場合は,和解成立の段階では出来る限り当事者の方に法廷に来ていただくようにしています。