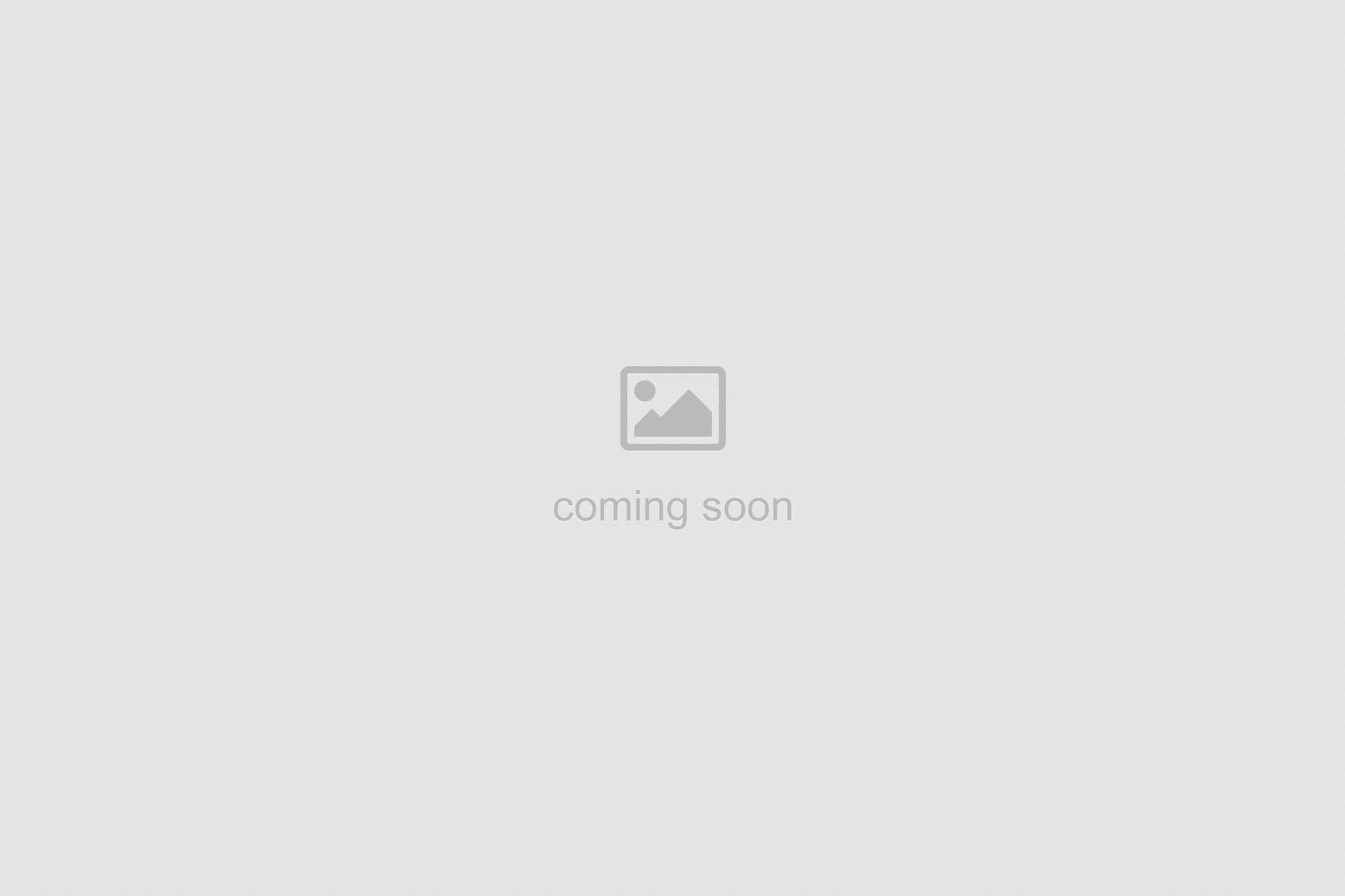日本人の法意識
時代劇と日本人の法意識
時代劇、つまり「水戸黄門」「大岡越前」「鬼平犯科帳」「必殺仕事人」「暴れん坊将軍」に代表されるような番組に、日本の法感覚が現れているところがあるように思うので、少し書いてみようと思います。
ちなみに、批判的な趣旨で書くわけではありません。私自身、幼少のころから時代劇を視聴するのは好きです。ただ、弁護士として実務をやってから改めて見てみると、いろいろ興味深く考えるところがありますので、ここで、雑談ですが書いてみます。
時代劇に特有の法則の一つは、主人公(達)が自ら事実を確認し、結果として事実認定を絶対に誤らないことです。
典型は「大岡越前」「鬼平犯科帳」でしょうか。人を裁いたり、または人を捕まえたりする立場の人物が、市井の町人たちと交流しつつ、そして時には密偵を使いつつ、事件の真相と黒幕を暴いていきます。
結果的に、大岡越前守や長谷川平蔵が犯罪事実の認定を誤ることは絶対にありません。
実は脅迫されて操られていただけの町人や元盗賊は必ず助かりますし(罰が科される場合でも、実は別の場所に行って新しい生活をせよという実質無罪放免)、黒幕は必ず成敗または厳しい刑をうけることになります。
ただ、実際にそのような裁判官や警察官がいてくれるかというとそうではありません。
もちろん、人間的に優れた方もたくさんおられますが、司法に関わる機関の職分は法律で定められていますので、時代劇のヒーローのように一から十まで真実発見のために動き回ってくれるかというとそうではありません。
それでも、何となく、日本人の中には今でも裁判官・警察官万能幻想というか、もっと言えば司法機関万能幻想とでも言うべき感覚がどこかにあるのではないかという気はします。
ただ、そういう期待を抱きすぎると、実際の事件の際には司法(弁護士含む)に幻滅することになるかもしれません。
民事事件の場合は、裁判官は争点となっていることの中で重要な事実について有無を判断すればよく、それ以上に微細な言動や行動について、何月何日に誰が誰に何を言ったとかどこに行った、その際の状況はどうだったというような細かい認定をするわけではありません。民事訴訟では、紛争を終局的に解決することが最重要視されるので、法的な主張たりえていない事項や、判決のために重要でない事項について逐一事実認定をすることはありません。
ここで、裁判官が真実解明のためとなれば現場でもどこでも駆けつけて真実を見つけてくれるのではないかというイメージを抱いていた人は、イメージと現実のギャップに戸惑うかもしれません。民事裁判を起こしたことのある人の中には、「何で裁判官は、現場に来て相手の言っていることが嘘かどうかをたしかめないんだ!」「代理人弁護士も、なぜ裁判官に対して現場を見に来るよう要請しないのだ!」と思ったことのある人がいるのではないかと思います。
勿論、建築訴訟等で必要であれば現場に来てくれることもありますが、まずは代理人弁護士から現場に来てもらう必要性を詳細に主張する必要があり、そうそうあることではありません。
建築訴訟等でも、大抵の場合は、写真を添付した報告書や、専門家に(自費で)現場を確認してもらった結果の意見書等を裁判所に提出することになります。また、裁判所が現場を見る必要ありと判断してくれた場合に行うのは、まずは鑑定人を選任して行う鑑定であって、本人が現場に来るわけではありません。
刑事事件についても、裁判官が現場に来ることは滅多に有りません。
警察が作成する詳細な実況見分調書で、現場の地理や状況等が立証されることになります。
弁護人にて事件現場について反証したい事項がある場合でも(事件当時の現場の交通量など)、裁判官に「現場を見てください」とは言いません。
まずは弁護人が現場に出向いて(その頻度自体も多くないですが)写真撮影をしたり、地理的な報告を作成して提出することになります。
ちなみに、批判的な趣旨で書くわけではありません。私自身、幼少のころから時代劇を視聴するのは好きです。ただ、弁護士として実務をやってから改めて見てみると、いろいろ興味深く考えるところがありますので、ここで、雑談ですが書いてみます。
時代劇に特有の法則の一つは、主人公(達)が自ら事実を確認し、結果として事実認定を絶対に誤らないことです。
典型は「大岡越前」「鬼平犯科帳」でしょうか。人を裁いたり、または人を捕まえたりする立場の人物が、市井の町人たちと交流しつつ、そして時には密偵を使いつつ、事件の真相と黒幕を暴いていきます。
結果的に、大岡越前守や長谷川平蔵が犯罪事実の認定を誤ることは絶対にありません。
実は脅迫されて操られていただけの町人や元盗賊は必ず助かりますし(罰が科される場合でも、実は別の場所に行って新しい生活をせよという実質無罪放免)、黒幕は必ず成敗または厳しい刑をうけることになります。
ただ、実際にそのような裁判官や警察官がいてくれるかというとそうではありません。
もちろん、人間的に優れた方もたくさんおられますが、司法に関わる機関の職分は法律で定められていますので、時代劇のヒーローのように一から十まで真実発見のために動き回ってくれるかというとそうではありません。
それでも、何となく、日本人の中には今でも裁判官・警察官万能幻想というか、もっと言えば司法機関万能幻想とでも言うべき感覚がどこかにあるのではないかという気はします。
ただ、そういう期待を抱きすぎると、実際の事件の際には司法(弁護士含む)に幻滅することになるかもしれません。
民事事件の場合は、裁判官は争点となっていることの中で重要な事実について有無を判断すればよく、それ以上に微細な言動や行動について、何月何日に誰が誰に何を言ったとかどこに行った、その際の状況はどうだったというような細かい認定をするわけではありません。民事訴訟では、紛争を終局的に解決することが最重要視されるので、法的な主張たりえていない事項や、判決のために重要でない事項について逐一事実認定をすることはありません。
ここで、裁判官が真実解明のためとなれば現場でもどこでも駆けつけて真実を見つけてくれるのではないかというイメージを抱いていた人は、イメージと現実のギャップに戸惑うかもしれません。民事裁判を起こしたことのある人の中には、「何で裁判官は、現場に来て相手の言っていることが嘘かどうかをたしかめないんだ!」「代理人弁護士も、なぜ裁判官に対して現場を見に来るよう要請しないのだ!」と思ったことのある人がいるのではないかと思います。
勿論、建築訴訟等で必要であれば現場に来てくれることもありますが、まずは代理人弁護士から現場に来てもらう必要性を詳細に主張する必要があり、そうそうあることではありません。
建築訴訟等でも、大抵の場合は、写真を添付した報告書や、専門家に(自費で)現場を確認してもらった結果の意見書等を裁判所に提出することになります。また、裁判所が現場を見る必要ありと判断してくれた場合に行うのは、まずは鑑定人を選任して行う鑑定であって、本人が現場に来るわけではありません。
刑事事件についても、裁判官が現場に来ることは滅多に有りません。
警察が作成する詳細な実況見分調書で、現場の地理や状況等が立証されることになります。
弁護人にて事件現場について反証したい事項がある場合でも(事件当時の現場の交通量など)、裁判官に「現場を見てください」とは言いません。
まずは弁護人が現場に出向いて(その頻度自体も多くないですが)写真撮影をしたり、地理的な報告を作成して提出することになります。
中華帝国と、日本人の法意識
J・K・フェアバンク著 大谷敏夫・太田秀夫訳『中国の歴史 古代から現代まで』(ミネルヴァ書房)に、中国の清王朝期の法意識に関する興味深い記述がありました。
以下、長くなりますが数か所を引用します。
(以下、引用)
同書248頁
「法は道徳の下位に置かれていた」
同書249頁
「一般的に、法は国内では主要なものでもなく普及しているものでもなかった。法の字義に訴えることは、真の道徳を無視するとか、あるいはその人の道徳性の弱さを認めることでもあった」
同書250頁
「十九世紀、西洋人たちは、個人を保護するための当然の過程が欠如している中国の制度に最も関心を持っていた。告発された者は、独断的に逮捕され、いつまでも拘留され、有罪と見なされたし、自白によって無理やり有罪にさせられ、弁護人の弁護も、弁明する機会も与えられなかった」
「正式の法が主として国家の利益に奉仕していたので、ただ非公式のままであった私法あるいは市民法は、この法律体系の中で発達していった。したがって、人々の間の争いの解決は様々な慣例、非公式な経路を通じて達成された。商取引や契約から生じる争いは同業組合か商人ギルドの中で解決されたであろう。隣人間の争いは、村の長老、隣保制、郷紳の構成員によって仲介されていたであろう。特に拡大した家族(宗教)あるいは宗族組織の長は、祖先崇拝の宗教的儀式を維持し、宗族構成員の子弟のための学校を支援し、彼らの結婚を取り決めるということに加えて、宗族を構成する者の税金納入を保証し、彼らの間の争いを解決することによって、構成員を法廷に出る必要のないようにあらゆる努力を払ったのである。結局、法律体系は表面的なだけのものであり、村での日常生活のレベルよりはるかに上にある政治の一部分でしかなかった。それゆえに、ほとんどの争いは古い慣習や地方の意見の調停や告発によって法律の領域外で解決された」
同書250頁~251頁
「このように西洋人に良く知られた方向に沿って中国の法が発達しなかったことは、旧中国において資本主義ならびに独立した企業家階級が発達しなかったことと明らかに関係があった。法人としての会社という考えはなかった。大きな商会は家族の仕事であった。取引関係は家族や家族から離れた世界での法律や契約の一般的な原理に支配された、冷たく非人格的なものではなかった。実業は中国人の生活を支えた交友関係、血縁関係の責務、そして個人的関係による網全体の一部分であった」
(以上、引用)
この文章を読んで感じたことは、現代の日本にも似通った部分があるのではないかということです。
日本は、近代にいたるまでは中国(中華的な帝国)の多大な影響の元に文化を形成しており、法においてもそれは例外ではなかったものと思われます。
日本が近代的な市民法(民法)を施行し、少なくとも法律の点について西洋的な方向へと転回を見せるのは1890年代のことです。
しかし、特に家族法分野においては、戦後の改革がなされるまでは、家族主義的な法制度が維持されました。
この点で、日本は西欧列強に追いつくために近代的な法整備を行いつつ、封建的・家父長主義的な(ひいては上記の中華帝国的な法にも通ずる)法制度を一部に残していたかたちになります。
現代においても、土地相続の事件処理のために、たまに戸籍を戦前の時代にまで遡って取得しなければならない時がありますが、そこでの戸籍は、現代の戸籍とは異なり、父・それを継ぐ男子(基本的に長男)を一家の主とした家父長制のものです。
それを、現代人の感覚から見れば「遅れている」「男女平等でない」「個人の権利が無視されている」となり得るところであろうと思われます。
しかし、ただ批判的に見るというのは、歴史に対する態度として必ずしもフェアではないと思うところもあります。
大半の日本人が生まれ育った農村を離れることなく、家族及び地域の助け合いのもとで生活をしていた時代は、法を説くよりも、家父長に強い権限を与えて構成員(家族・地域社会のメンバー)に道徳(法とイコールではない)を遵守させることが、社会秩序を保つための手段として有用であった時代も、あったのであろうと思います。
現代においても、古くから地域社会の中で暮らす高齢の方などには、紛争に対する弁護士の介入や、裁判による紛争解決そのものを忌避するという傾向が見受けられることがあります。
家族的・地域的な繋がりを維持して助け合っていくためには、法による解決など有害無益、今後とも良好な関係を持続していくためには多少の不満は飲み込んで、また有力者の言うことに従っていれば基本的に間違いはない、という意識が、その根底にあるのではないかと思うこともあります。
しかし現代は、法律と契約に基づいて私人間の利害関係が調整・解決される時代となっており、交通・通信手段の発達により、古くからの地域社会にも法律と契約は容赦なく浸透していきます。法に頼らない、旧日本的な秩序による解決が望ましい場合も時にはあるかもしれませんが、基本的には法と契約の解釈による解決がなされることが望ましい場合が今後さらに多くなっていくと思われます。
パワーハラスメントと法意識
学術的な根拠があって言うのではありませんが、ブラック企業やパワーハラスメントの問題というのも、日本人の、法や道徳に関する前時代の考え方と、近代的な権利意識との邂逅と対立という側面があるのではないかと感じることがあります。
会社内、いわば「ムラ」社会の有力者に対して、いちいち労働基準法違反だ、パワーハラスメントだと文句をつける者よりも、会社内の良好な人間関係を維持していくことに心を砕き、多少の不満は飲み込むこと、そしてできれば有力者の庇護下に置かれることが、生き方として実用的(処世術)という感覚がどこかにあるのかもしれません。
会社(株式会社)というのは、源流はイギリスの東インド会社ですから、由来としては間違いもなく西洋の制度です。会社と従業員との関係を規律するのも、これも西洋伝来の労働契約です(必ずしも書面ではない場合もありますが、法律上は労働契約による使用者・被用者の関係があります)。
そんな西洋的な会社制度・労働法規の中で、封建的・家父長主義的(そして旧日本的)な名残を感じさせる個人あるいは集団の行動選択が見られることがあるという現象は、勿論、事件は事件として個人の人権を保障するかたちで解決されねばならないとしても、考察の対象として興味深いところがあるように思われます。